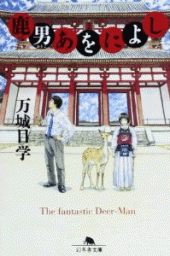◎鹿男あをによし
◎鹿男あをによし
万城目学
幻冬舎文庫
これを読むなら今しかないだろう。ということで実は以前より射程に入れていた万城目学『鹿男あをによし』を読んだ。いやはや面白かった。この感想を書くために文庫本を取り出すと、また知らずの知らずのうちに読み出してしまうから困ったものだ。
【大学の研究室を追われた28歳の「おれ」。失意の彼は奈良の女子高に赴任する。ほんの気休めのはずだった。渋みをきかせた声で鹿が話しかけてくるまでは。「さあ、神無月だ―出番だよ、先生」。ちょっぴり神経質な彼に下された、空前絶後の救国指令とは!?】
何故、今、この小説だったのかといえば単純な話、三月末に奈良に行ったから。そこで春日大社、興福寺、東大寺などをめぐり、悠久の古都を大いに堪能することが出来た。
文中に「春日大社の森は古い(中略)鬱蒼たと茂る木々に光を遮られ、しんと静まった森をのぞいていると、何やら人知の及ばぬ雰囲気を感じる。単に古いという言葉では到底表現出来ない何かがある。木を集めて森という字を作ったのなら、古という字を三つほど重ねないとこの厳かさは表せないような気がする」とあるが、それは自分が目にして漠然と感動していたことを、作家が明瞭に表現してくれたような気がして、それだけで奈良に行ってから本作を読んだのは正解だと思った。
そして春日大社の幽玄も大仏殿の絢爛もそこが奈良であることを証明していたのが鹿たちの群れだった。今まで鹿のことなどろくに考えもしなかったが、今も鹿の可愛さ、鬱陶しさがずっと頭から離れないでいる。
それでは奈良以外に何故この小説を射程に入れていたのかといえば、純粋に万城目学という作家への興味だ。前作であるデビュー作『鴨川ホルモー』がまあまあ面白かったこともあるが、三つ違いでもう一人の京大出身の森見登見彦と合わせて30代の新進作家を追いかけてみるのも一興だと思っている。
「ホルモー」も「鹿男」も作風はトリッキーだが、万城目学は本作も含めて直木賞の候補になること4回。かなりの実力者だといっていい。
さて、この小説はその鹿になってしまった女子高校の代用教師を主人公とする物語だ。
なんじゃそれ?てなものではある。『鴨川ホルモー』を読んだときもなんじゃそれ?だったのだが、今回は前作の京都の大学生たちの「密室の遊戯」的な世界観を壮大にスケールアップして鹿男が日本を滅亡から救うという物語になっている。
いくらなんでもそこまで壮大なファンタジーに仕立てなくてもいいではないかとも思うのだが、内へ内へと閉じながら異空間を作り上げるイメージの京都に対し、外へ外へと悠久に広がっていくイメージの奈良が舞台であることですべてが「あり」になってしまうのだと思う。
当然、その「あり」にはある程度の説得力が加味されていたことはいうもでもなく、「あり」に至るまでの万城目学の巧みな構成力のたまものではあるのだが。
物語は「君は神経衰弱だから」の教授のひと言で、研究室を追われ奈良県の女子高に赴任させられといわれる「おれ」のエピソードから始まる。本人にとっては痛恨の挫折なのだろうが、小説の書き出しとしてはなかなか静かな立ち上がりだ。
「ホルモーという言葉は、少なくとも先の大戦以降数十年の間、さらにはそれ以前-大正、明治、江戸、安土桃山、室町、鎌倉、平安-の時代において知る者だけが知り、伝える者だけが伝え、かつて王城の地、ここ京都で、脈々と受け継がれてきた」と、いきなりメーターを振り切ったような大上段からのハッタリで始まった『鴨川ホルモー』と違って、『鹿男あをによし』はギアを換えて次第にメーターを上げて行く展開になっている。
私は気がつかなかったのだが、そこから「おれ」の女子高での展開は夏目漱石の『坊っちゃん』がモチーフになっているらしく、あの主人公に山嵐や赤シャツ、マドンナが絡んでくるのと同じようにエトランゼの「おれ」は様々な人たちと触れ合っていく。
ローギアのうちに下宿のおばあさんや同僚教師などリチャード・ギア似の教頭以外、さしてエキセントリックな性格ではないキャラクターがすぅーと頭の中に入っていくのは、万城目学の筆力というものだろう。
そこに現れるのが、「おれ」の神経衰弱を加速させる女生徒の堀田イトだった。
どうやら自分はこの娘の底知れない魅力にやられてしまった。彼女は地層で暴れる大なまずか、なまずを踏んづける鹿島大明神なのか。はっきりいってしまえば『鹿男あをによし』の面白さの八割方は堀田イトの魅力に満ちたキャラクター造詣にあるのではないかと思っている。
「おれ」と堀田イトの距離が近づいたり離れたりする進行にやきもきしながら、下手をすればイトをもっと知りたいという願望の方が“サンカク”やら“目”やら、“三角縁神獣鏡”の謎解きやら、ついには日本を襲う壊滅的な危機すらもどうでもいいと思うようになっていた。う~ん困ったものだ、これはあまりよい読書傾向だとはいえない、それほど自分はこの“野生的魚顔”に惚れこんでしまったのだろう。
その堀田イトが八面六臂の大活躍をする「大和杯」での剣道の試合は迫真に満ちていた。中盤のクライマックスといってもいい。『坊っちゃん』から壮大な歴史ファンタジーに至る途中に突如現れる青春スポ根の世界だ。
ここでの彼女は絶対的なヒロインと化す。スポーツでの英雄に恋心を奪われる心理というのは女の子だけではないことは小学生のときの自分が一番よく知っている。
「負けることもあるだろう。怖いと感じることもあるかもしれない。別に怖くなってもいいんだ。ただ、やる前からあきらめるな。それは相手に負けたんじゃない。自分に負けただけだ」。いよ!いいこといってるぞ「おれ」。
きちんと「おれ」の成長物語になっている構成も憎いばかりだ。
その大和杯を挟んですらもなかなかフランクになれない「おれ」とイトだが、そうこうするうちに日本に迫ってくる未曾有の危機。
すべての謎が明かされるクライマックスの舞台は平城京。このたびは近鉄電車の車窓から眺めただけだったが、次に奈良に行く機会があれば、ぜひあの地に足を踏み入れてみたい。
そして映画『転校生』のエンディングを思わせる胸がキュンとするようなエピローグ。
これだけ「やられた感」に満ちた読書は久々のことだった。
a:1471 t:2 y:1