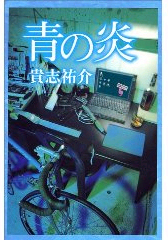◎青の炎
◎青の炎
貴志祐介
角川文庫
【高校生・秀一の家族に粗暴な闖入者が現れた。母が十年前、再婚しすぐに別れた男だった。警察も法律も家族の幸せを取り返してはくれないことを知った秀一は決意する。一家団欒の平和を取り戻すために、自らの手で男を葬り去ることを…。】
石田衣良『4TEEN』を読み終えてから、本作にとりかかったものの遅々として進まず、途中で別の小説に浮気しながら、ほぼ一ヶ月かかって読了した。
勉強も出来て、優しい母親と可愛い妹がいて、ほどよく性格のいいクラスメートにも恵まれ、気になるガールフレンドもいる。好きなことは鵠沼から由比ヶ浜の高校まで江ノ電よりも早く湘南海岸沿いの国道134号線をロードレーサーで滑走すること。
そんな過不足のない青春時代を謳歌している高校生が完全犯罪を計画する。飲んだくれで粗暴な元義父から家族を守らなければならない。この物語には「痛み」がある。
もともと事件を犯罪者の側から描く倒叙推理ものというのは、読み手と主人公が共犯意識で結ばれることになるので、通常の探偵小説とは比べものにならないほど切迫した緊張感が伴う。私は決してこのジャンルは嫌いではなく、大学時代にはクロフツの『クロイドン発12時30分』などを夢中で読んでいたものだが、さすがに十六歳の少年が殺人を冒す話となると、その「痛み」の描写にいたたまれない思いもあって読書がしばしば中断していた。
なお、この『青の炎』は二宮和也の主演で蜷川幸雄が映画化しているのだが、おそらくテレビで放映されていても観ることはないだろうと思う。具体的な映像で「痛み」を追体験する気にはとてもなれないからだ。
誰だか忘れたが、ある推理作家が「倒叙ものはより文学的である」と語っていたのを聞いたことがあるように、犯罪者の達成感も後悔も懺悔も含めて、その心理描写はより克明に描かれることとなり、殺しの場面も当事者による進行形で実行される以上、探偵の推理にで再現される現場とは比べものにならないほどリアルな描写となる。つまり倒叙ものは作家の筆致も問われるということになるのだろう。
貴志祐介に関して、この「読書道」では初登場なのだが、以前に『黒い家』という出世作を読んでいる。あれはジャンルとしては恐怖小説に近かったのだが、犯罪者の異常心理を考察する場面で、子供の頃に書いた作文を引用する場面があり、それが何やら恐怖感を助長されるものがあり忘れられないのだが、最後に殺人鬼が迫ってくるクライマックスなどのたたみかけも巧く、かなり「書ける」作家だという印象がある。描写力に自信のある作家であるならば倒叙ものは挑戦してみたいジャンルなのだろう。
本来なら、こういう小説は長い時間をかけて少しずつ読んでいくのではなく、出来るなら集中して一気読みしたほうが、よりサスペンスフルな気分に浸れたのかもしれない。
ただ『青の炎』の櫛森秀一という十六歳の殺人者について、いくら倒叙もの特有の共犯意識を喚起させられたからといって、その行動に対して肯定と拒絶が相半ばしてしまう部分もあった。正確にいえば殺人の動機については共感するものの、思考については受け入れ難いことも少なくはなかった。これは私と十六歳の少年とでは世代的にギャップがありすぎるということもあるが、貴志祐介の意図でもあったのではないかと思えるのは、秀一が殺人に駆り立てられるまでに追いつめられていたことは間違いないとしても、一面では完全犯罪計画に陶酔しているのではないかという心理も散見できること。殺人計画に“ブリッツ”や“スティンガー”というネームをつけ、殺害行為を“強制終了”と表現するあたりに少年独特の恐さが描出されている。秀一が自らの行為に対して揺れ動くのと同様に、読者の共感も乱高下するのだ。
完璧なはずだった殺人計画に綻びが生じ、事態が次々と暗転していく過程はミステリーのルーティンとして読ませるものの、総じて少年・秀一の「罪と罰」に比重が置かれた青春小説という見方が正しいのかも知れない。
面白かったのが、夏目漱石『こころ』が引用されていたこと。あの小説での「先生」と「K」の心理について秀一は考察し、殺人から、いずれは自滅していく自分を想像していく。ついこの間『こころ』を読み終えたばかりだったので、この偶然の符合にはドキリとさせられた。
a:2978 t:3 y:2