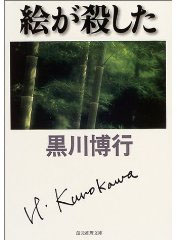◎絵が殺した
◎絵が殺した
黒川博行
徳間文庫
“「帳場はここ富南署に置く」−帳場とは関西の刑事仲間の符牒で捜査本部のことをいう。捜査一課長や刑事部長の意を受けて、府警本部長が設置するのである。大阪府警察捜査一課には全部で十の班があり、このうち、強盗事件犯、火災専門犯、特殊捜査班の三班を除くあとの七個班が殺人事件を担当する。各班は警部を長とし、その下に警部補が一人ないし二人、あとは巡査長八、九人の計十人から十二人編成となっている。班は事件発生と同時に、その事件発生地を管轄とする警察署に派遣され、事件が警察の規定でいう「本部長直接指揮事件」となれば、そこに帳場が設置されて部屋と電話が貸与される。また、署から十人ないし二十人の応援捜査員をもらえる−。”
少々長々と引用してしまったが、大阪府警捜査一課シリーズに必ず出てくる「お約束」の文章だ。私はこの「帳場」の説明文をいつしかワクワクしながら読むようになり、頭の中に勝手に駆け巡るBGMに乗ってこれを読みあげるナレーションが聞こえてくる。今月はその大阪府警捜査一課シリーズを貪るように食ってきたが、そろそろ黒田博行の作風転換期に近づいて残りも少なくなってきた。そうなるとこの「お約束」が読めなくなるかも知れず、寂しい限りなのだ。
【竹の子採りの主婦が発見した白骨死体。身元の確認は難航するかに思われたが、丹後半島の岬の上で消息の絶えていた日本画家と判明した。背後には過去の贋作事件と贋作グループの存在が見え隠れし、第二、第三の事件が発生。大阪府警捜査一課の吉永は怪しげな美術ブローカーともに事件を追う】
竹林に埋めた死体を成長した竹の子が地面に押し出すという衝撃的な場面で事件は始まる。今回の主人公(記述者)は大阪府警捜査一課・深町班の吉永誠一刑事。仲間うちからは「誠さん」と呼ばれており、『海の稜線』『ドアの向こうに』の総長・ブンのコンビの陰で脇役を演じていた男だ。なかなかの理論派であり、デコと呼ぶ恋女房がいる。短編集『てとろどときしん』では主役のエピソードもあり、そのエピソードを読んでいてつくづく良かったと思う。主役に感情移入できるかどうかというのは私の読書には重要な要素である。
余談だが、この吉永誠一刑事は船越英一郎主演で『刑事吉永誠一・涙の事件簿』というタイトルで2時間ドラマとしてシリーズになっていたらしく、何と舞台は神奈川県警に置き換えられ、吉永が登場しない『雨に殺せば』『切断』なども吉永のシリーズとしてドラマ化されているようである。
このことからも、安直な映像化なんだろうなぁ〜と予想してしまうのだが、実際に本屋の文庫本棚に【黒川博行】という仕切りで陳列している書店は数えるほどで、この作家の一般的な知名度はどの程度なのかと思うときもある。私としては『疫病神』が最も知れ渡った黒川作品だと思っていたが、案外、吉永刑事の原作者として名前を憶えられているのかも知れない。ただ船越英一郎ファンの主婦が「原作でも読んでみようかしら」とページを開いた途端、目に飛び込んでくる大阪弁のテンポと捜査一課の帳場の雰囲気に呆然となること請け合いだろう。
黒川作品は事件が勃発する舞台を徹底的に調べ上げ、その正確な背景の中で意表をつく物語を仕掛けるというのが持ち味である。これは初期作品の本格推理ものから現在のハードボイルドな作風まで一貫している。そのあたり東野圭吾をして「最も信頼できる作家」といわしめる所以なのだろうが、確かにこの『絵が殺した』でも日本画壇の裏に潜む伏魔殿のような業界のからくりが精緻な描写で語られており、重厚と軽快のコラボレーションで物語を転がしていく。
正直いえば刑事が容疑者のひとりとコンビを組んで捜査に乗り出す展開はやり過ぎだったと思うし、真犯人のアリバイと密室殺人を崩すきっかけとなる種明かしも高尚なものとはいい難い気もした。しかし、例えば土砂降りの中をずぶ濡れになって事件現場まで走る刑事たちの以下のやりとりを思い出すとどうしても口元が緩んでしまい、四の五のいっても仕方がない気にさせるのだ。
「こういうとこ、うちのよめはんに見せたいもんやで」
「亭主がどれだけ辛いめして給料運んでくるか、ちょっとは感じ入るやろ」
「うちのはもう寝てまっせ」
「今さら手入れのしようもない顔を一所懸命マッサージして、ちょうちんみたいな赤い帽子かぶって、ついでに屁のひとつもひって高いびきや」
大阪弁の会話が面白いのは当然だとしても、ここから漂う刑事たちの滑稽さと純情ともいえる使命感がとても粋なのであって、社会派ドラマでもあり、本格推理ドラマでもありながら、きちんと人間のドラマに着地している点が黒川博行の素晴らしい点だと思うのだ。
a:2261 t:2 y:1