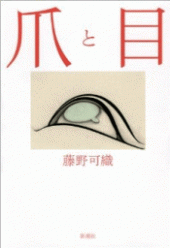◎爪と目
◎爪と目
藤野可織
「文藝春秋」九月特別号(平成二十五年)
例の如く「文藝春秋」誌に全文掲載された芥川賞受賞作を読む。いや「例の如く」といいながら三月号掲載の(つまり前回の芥川賞)の黒田夏子『abサンゴ』は1ページも読まない内に挫折しているので、恒例になりきれているわけではないのだが・・・。
【 「あなた」は目が悪かったので父とは眼科で出会った。やがて「わたし」とも出会う。その前からずっと、「わたし」は「あなた」のすべてを見ている――。三歳の娘と義母。父。喪われた実母――家族には少し足りない集団に横たわる嫌悪と快感】
これも雑誌を買ったまましばらく放置していた。どうも読書のペースが落ちていることもあって、本への訴求が脆弱な時期に純文学を読むのはきついと思っていた。
そうこうしている内に次の芥川賞が決まってしまい、追われるように1月も終わりかけたところで第149回芥川賞受賞作・藤野可織の『爪と目』を一読した次第。
一読。そうまさに一読した。
かつて私はある芥川賞作品を読む際に「怠惰な読書空間のある種の刺激として恒例化」していると書いている。ある種の刺激とは純文学の洗礼と言い換えてもよいが、恒例化したおかげで、純文学も大衆文学も物語小説の括りの中で差異を見つけ出す作業そのものがまったくの徒労であることを実感するようになっていた。
「畢竟、どれだけ御託を並べようが、つまるところ“面白いか面白くないか”の二元論に収斂されるのではないか」などと思ったのだが、その二元論に従えば『爪と目』が面白かったかどうなのだが未だにはっきりせず、実体はチャラい本読みの私にとっては短いセンテンスでスラスラ読めることが何よりも有難いことだと言ったら情けなさ過ぎるだろうか。
この作品の最大の特筆は三歳児の視点から、「わたし」と「あなた」の二人称で父親の愛人を詳細に観察していることが挙げられている。賞の選考委員の選評を見ても、ネットの読書レヴューを覗いてもその二人称であることに問題は集中しているといっても良い。
三歳といえば少女以前に幼女だ。そんな幼女が父の愛人を詳細に語っていく展開は驚きといえば驚きではある。
どうも前回受賞の『abサンゴ』が全編平仮名で書かれているのが話題になるなど、現代の純文学シーンは文体の実験に特化しているのかもしれない。選評で村上龍が「意匠を凝らすというのは、リアリズムからの意図的な逸脱ということだ(中略)程度の差はあるが、読む側は戸惑いと負荷を覚える」と語っているように、物語よりも文体の実験が先行するのはあまり好きな風潮ではない。
……ところで「二人称」とはなんだろう。浅学な私には一人称、三人称はわかっても、二人称といわれると熊さんと八つぁんが掛け合う落語しか思い浮かばないのだが、『爪と目』が二人称であるならば、全編、三歳児の「わたし」が語る「あなた」への批評であるので、これは一人称ではないのか?と思ってしまうのだが、それにしては「わたし」が知りえない「あなた」の実母とのやりとりや浮気相手との顛末も「わたし」が描写していくのはどうしたものだろう。これが二人称というものなのだろうか。
ただ、「わたし」は三歳児の「わたし」ではなく、「あなた」を観察し続けて来た「わたし」を三歳児当時の「わたし」に仮託して書かれた批評であることは疑いのないことだと思うので、「わたし」が知りえない「あなた」の事象については、時間の流れの中で蓄積された脚色も含まれているという意味で許容範囲であるかもしれない。だから『爪と目』は村上龍が語るところの「リアリズムからの意図的な逸脱」とばかりもいえない気もした。
一方でこの作品をある種のホラーと見る向きもあるようだ。確かに怖い。三歳児が語る大人の世界というファンタジーの要素以上に、三歳の「わたし」は完全に「あなた」を見切っている。この批評の辛辣さの黒さは、それは「あなた」がそれほどエキセントリックな存在ではなく、どちらかといえば俗物であるがゆえに際立っていく。
最後の目に異物を押し付けることで同化する「わたし」と「あなた」。その意味するところが理解出来ないで終わってしまったのは残念だった。
a:1372 t:2 y:0