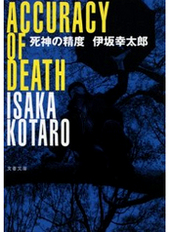◎死神の精度
◎死神の精度
伊坂幸太郎
文春文庫
「最近、雨が多いですね」「俺が仕事するといつも降るんだ」「雨男なんですね」
ごく当り前の日常の中で、何てことのない会話が交わされる。
ところが伊坂幸太郎の場合はこれが三年後に地球が滅亡する世界だったり、会話の主が殺し屋だったり、銀行強盗だったりする。そして表題が示すように今度は「死神」だ。
【音楽を愛し、仕事はクールに確実にやり遂げる。7日間の調査の後に対象者の死を見定める死神が出会う6つの物語。】
『死神の精度』というタイトルでも、普通なら死神という言葉は比喩や隠喩で用いられることの方が多いのかもしれない。しかし私も既に伊坂幸太郎を9冊読んだ。
「死神とタイトルにつけているのだから、死神が出てくるのは当り前だ、そうだろ?」伊坂調で書けばそうなるのか。
所謂、髑髏マスクに黒頭巾で鎌を持つ死神ではなく、死神のパーソナリティは伊坂ワールドの中で定義される。まず死神の「私」は、死神という職業に就く勤め人であり、調査部から指名された人間に死を与えるべきかどうか、その時々のシチュエーションに合わせた人間として対象者に接触して、7日間以内に「可」か「見送り」かを判定し、死を見定めることを業務とする。
そして、彼らは病気や自殺には関与しない。あくまでも災害による不慮の事故などが彼らの仕事となる。だから「癌という死神に蝕まれて・・・」などという表現を使われると「一緒にしないでくれ」と憤りを覚えるのだという。
一方「人間が発明した最大の功績はミュージックだ」というほど音楽を愛する。しかしCDショップで音楽の視聴を楽しんでばかりいると監査部の抜き打ち検査が入ることもある。どうやら業績についてはそれなりの査定があるらしい。
以上が伊坂幸太郎の定義した死神であり、いわば『死神の精度』という小説のレギュレーションということになる。
伊坂作品は通奏低音に“神様のレシピ”を設定し、人はある種の法則で運命を決められているのだというモチーフで物語が展開されているものが多いが、バラバラのピースを嵌めて完成したパズルを見せたのが『ラッシュライフ』であるならば、『終末のフール』や本作などはすでに完成しているパズルの製作過程を逆回転してピースを見せる作品なのかもしれない。
読んでしばらくして気がついたのだが、主人公は死神という神様であり、本作はその意味で神の目線で描かれた小説だということになる。これが死を自覚した人々が織りなす日常を描く『終末のフール』と違う点だろう。
『死神の精度』ではメイン人物の死を知る者は死神の「私」と読者に限られるのだが、死を自覚しない人々の“死に目”を知ることは予想した以上に不思議な感覚だった。そう、この小説の各主人公は死ぬ運命になければならない。
表題の『死神の精度』の陰気なクレーム対応係のOLは、寸でのところで「死」が見送られる。これはあくまでも特殊な例で、『死神と藤田』の極道者も、『吹雪に死神』の息子を死に追いやられ復讐を計画する婦人も、『恋愛で死神』のストーカーに狙われている女性に恋焦がれる真面目な青年も、『旅路を死神』の殺人容疑で逃亡している若者も、『死神対老女』の70歳になる女理髪師も、本来のドラマツゥルギーでは死の裁きを受ける必要がなさそうな人物たちでも死神は「可」の判定を下していく。
神様は少々のヒューマニズムなどではブレないのだといわんばかりだ。
この小説のユニークな点は、本来ならばドラマチックな見せ場となりそうな「可」と「見送り」の判定の場面をクライマックスとして機能させない点にある。
言い換えれば伊坂幸太郎は「生」か「死」かという究極の選択にはまったく興味を示さず、また死に行く者たちへの慈しみも薄い中で、どちらかといえば死神が人間の「生」を観察する様を面白がっている風にもとれるのだ。
人の一生で死は劇的なドラマであるが、死ぬことそのものは誰にでも起こる人生の既定路線であり、劇的の装飾を取り除いてしまえば、そこに残るものはただの日常以外の何物でもない。
死神はいう「人が生きているうちの大半は、人生じゃなくて、ただの時間、だ」と。あるいは「死ぬのが怖いか?ならば生まれる前は怖かったか?」などと尋ねてくる。
死という単純にして深遠なテーマがあるならば、当然、人間とは何ぞやという設問に行き着く。そして伊坂幸太郎の見事なところはその重厚長大な(?)テーマをちらつかせながらも、面白主義の一歩手前の位置で悠然と立っていることなのではないか。
全部の話がそれぞれに面白かった。そしていえるのはすべてが連作短編として丁度よいサイズだった。
吹雪に閉ざされた山荘というクローズド・サーキットを作り上げて、宿泊客が一人、また一人と殺されていく『吹雪に死神』では、死神が探偵役として活躍する。おや、まともに“本格”をやるつもりかいなと思いきや、この連作でなければ成り立たない真相がオチになっていて笑わせるし、『旅路を死神』などはロードムービーの面白さが随所に散りばめられ、まるで70年代の藤田敏八か長谷部安春の日活映画を彷彿とさせる。この話だけでも十分に映画化が可能なのではないか。これくらい書ければ作家生活も楽しいに違いない。
このように各エピソードで死神の調査の対象となる人間たちはどれも魅力的な人物として描かれていながら、容赦なく「可」を与え続ける死神。
死神は常にクールに客観描写の中に時折、自分の所見を挟むだけで、感動描写を決して感動的に伝えることはしないのだが、話がみるみる感動的になっていく不思議。
例によってエピソード同士のリンクも鮮やかに決まり、とうとう私もこういう部分に伊坂光太郎の典型を見るまでになってしまったか。と思った。
a:2212 t:2 y:1