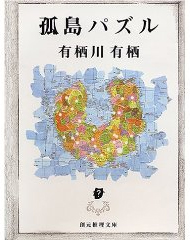◎孤島パズル
◎孤島パズル
有栖川有栖
創元推理文庫
【英都大学推理研の紅一点・マリアと共に南の孤島へ赴いた江神部長とアリス。島に点在するモアイ像のパズルを解けば数億円のダイヤが手に入るとあって、宝捜しを始める三人。折悪しく嵐となった夜、滞在客のふたりが凶弾に斃れる。無線機が破壊され、絶海の孤島に取り残されたアリスたちを更なる悲劇が襲う!】
『月光ゲーム』では突然の噴火によって退路を断たれたキャンパーたちを襲う連続殺人だったが、『孤島パズル』では奄美大島より南に50キロに浮かぶ孤島での連続殺人となっており、文庫版を開くと二つ折りにされた“嘉敷島”のマップが挟み込まれていた。
作家が、ストーリーやそこに用いるトリックに都合のよい舞台装置を設定することが自由に容認されているあたり、大衆小説のジャンルの中でミステリーが特異な存在感を際立たせている所以なのかもしれない。
前回、私はクローズド・サークルについて、作家が科学捜査の不介入となる状況を強引に作り出して、大きなのリスクを回避しているのだから、とことん心理の極限を描きこむことは読者への礼節なのではないかとを書いた。
「心理の極限」はいささか大袈裟な表現だったかもしれないが、最低でも「物語」としての面白さがなければならないとは強く思っている。トリックを披露してそれを解明してみせるだけの問題集のような「本格」は私の趣向ではないのだ(頭が悪いというのもあるのだけど)。
その点で有栖川有栖の小説にその杞憂がないことがわかったばかりか、文体と作品世界に惹かれるものを感じていたので、江神二郎&学生アリスのシリーズを続けて読みたいと思った。そういう信頼感というのは実に重要なことなのだ。
それにしても本屋で手にとって文庫本裏表紙のストーリー紹介に目を通したとき、「また、こんなヤツかいな」と苦笑してしまったが、結論として『孤島パズル』は愛すべき作品として幸せな読書時間をもたらしてくれたのは確かだった。
そもそも舞台装置といっても、時計館、斜め屋敷、人狼城のようなマジシャンが魔術を披露するための大道具のようなものではない。何よりもサブストーリーとして、モアイ像に秘められた五億円の宝探しというお楽しみも盛り込まれているのだから、孤島のマップがあるのはいかにものお楽しみで、それも複雑怪奇なものではなかったので大いに安心した次第。
何よりも登場人数がタイトであることがいい。デビュー作は物語のサイズにしてはあまりに登場人物が多すぎた。登場人物がタイトになれば、当然、物語もスマートになり、その分だけ各々の個性が際立ってくる。作品世界の密度は『月光ゲーム』とでは歴然としていたのではないか。
そのスマートな物語と密なる人物設定の背景を彩り、作品全体に色を与えているのが真っ青な南国の海の広がりだった。笑われるかもしれないが、私はページをめくりながら頭の中でニーノ・ロータかミシェル・ルグランのメロディを奏でていることもあり、かなり忠実に小説世界の映像を思い浮かべていたように思う。
展望台から臨む波光きらめく大海原に弾けた若者たちは、月が波間に浮かぶ夜の海の中に閑かに溶けていく。本格ミステリーの書評にはそぐわないのかもしれないが、アリスとマリアが月夜の海にボートを浮かべ、中原中也の詩を諳んじる場面は私には圧巻だった。その後にボートが転覆して、静寂がぶち壊れることを面白がれる恋愛感情未満のお互いの空気感などはなかなかリアルに読ませてくれるではないか。
有栖川有栖を信頼できるというのはこういう描写を掌にしているからに他ならない。
もちろんこの小説は、連続殺人事件の真犯人を学生名探偵・江神二郎が暴き出すことに、すべてのロジックが収斂させていく構造となっており、これが前作に続いて「読者への挑戦」が用意された本格探偵小説であることに帰着する。
「作者は、江神二郎が読者と同じ条件の下にたった今犯人を知ったことをお知らせするとともに、読者に挑戦する。あなたは犯人の名を直感ではなく、推理によって特定することができるはずだ、と。謎のすべてに答えを見出すことはできずとも、犯人は判る。ここにパズルがある。どうかあなたの手でこの小宇宙に秩序をもたらしていただきたい。」
『孤島パズル』とはよく名付けたもので、有栖川有栖は真夏の南国での青春のひとコマという余韻を醸しつつ、モアイ像にまつわる宝探しからジグソーパズルに興ずる人々を描写しながら、旺盛にクローズド・サークル、密室、アリバイ、ダイイング・メッセージというパズラーの要素がふんだんに散りばめていく。
私は作家と推理対決をする気などまったくなく、例によって挑戦状もあっさりとスルーしてしまう軟弱な読者であるので、一旦ページを戻して自分なりの推理を組み立てるなどという徒労はしないのだが、クライマックスの江神二郎の論理が圧巻のうちに展開されていく過程で、思わず巻頭に二つ折りで挟み込まれた地図と睨めっこしてしまった。
とくに鬼面人を驚かすようなケレンなトリックがあるわけでもないので、私のような頭の悪い読者でも密室、アリバイ、ダイイングメッセージのすべてを理解することが出来た。そして真犯人が明かされるときに小説の緊張感は最高潮に達していく。
このあたりの江神とアリスのやり取りの中で真相が浮き彫りにしていく筆致はなかなかのものだ。名探偵と殺人者との間に流れるの空気は、やがてあまりにも広大な大海原に哀しくのみ込まれてしまうのか。
少々、褒めすぎてしまった感がなきにしもあらずだが、欲望、嫉妬、復讐といった人間の原罪を太陽と海と月が静かに見つめていたような読後感はしばらく尾を引いていくような気がする。傷心のマリアのことも気になって仕方がないので、このシリーズを更に読み続けていくとしよう。
a:2057 t:2 y:1