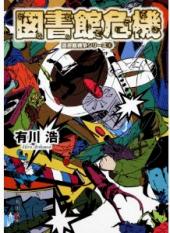◎図書館危機
◎図書館危機
--- 図書館戦争シリーズ③
有川 浩
角川文庫
【憧れの“王子様”の正体を知ってしまった郁は完全にぎこちない態度。そんな中、ある人気俳優のインタビューが、図書隊そして世間を巻き込む大問題に発展。加えて、地方の美術展で最優秀作品となった絵画が検閲・没収の危機に。特殊部隊も警護作戦に参加することになったが!】
有川浩が女のダークな内面を描いて見せることは前頁でも触れたが、前作の『図書館内乱』で査問にかけられた郁が女子寮の中で陰湿な疑心に晒される場面があり、この『図書館危機』でも郁が出動した茨城県展警備での女子寮の確執が描かれている。
確かにいじめは男にもある。男のいじめと比べて女のそれが殊更に陰湿であるとは思っていないが、女性作家が描く女の内面があまりにも容赦がなく、有川浩には何かトラウマがあるのではないかと邪推してしまうほどリアルに迫ってくる。いやリアルかどうかも私にはわからないが、少なくとも女の陰湿な悪意には悪意で返すという強い意志が込められているのは間違いないのではないか。
そういうヒヤリとした書き味が、このシリーズを単なるラブコメや荒唐無稽なミリタリー小説とは一線を画す読み物として成立させているような気がする。
さて、大雑把にこのシリーズをまとめると、ヒロインの笠原郁がどのように成長し、どのタイミングで堂上篤との恋を成就させるのかとなってしまうのだが、前作のラストで“王子様”の正体を知って、「・・・だっから、きゅんとか鳴るなAカップの分際で―!」と動揺しまくりの郁のドタバタを翻弄するように次から次へと事件を仕掛けていく語り口は相変わらず上手い。
その第三巻のクライマックスは茨城県展における良化特務機関との大規模な戦闘であり、図書基地指令・稲嶺の勇退ということになる。
戦闘場面も『海の底』に収録された「前夜祭」の無為な戦闘シミュレーションとは長足の進歩といえるほどの迫力で描かれていたし、稲嶺が自ら身を引く場面のしっかりとした説得力は十分に腑に落ちるものであったのだが、図書特殊部隊の信条でもある「あらゆる業務に精通し対応する」というモットーのもと、郁が思わぬ才能を発揮する昇任試験での実技試験のエピソードなどが読んでいて楽しかった。
そう、このシリーズの根底には登場人物が軍隊の兵士ではなく、あくまでも図書館の職員であるという前提があり、その根拠として作家のキメ細やかな図書館業務への豊富な理解がある。こうしてシリーズを追いながらも有川浩によって教育機関として多岐にわたる図書館員の仕事を図らずも教えてもらうことになる。
そして最も面白かったパートが言葉狩りの問題を描く『ねじれたコトバ』だろう。この章はシリーズでも白眉の出来栄えだったのではないか。
「週刊新世相」に人気急上昇中の若手俳優・香坂大地のインタビューが舞い込む。かなり赤裸々に半生を語るということでヒット間違いなしの企画を任された折口マキだったが、過不足なくインタビューを終え、校閲も終了してゲラを上げた後で香坂側からストップがかかる。発売延期の申し立て理由はインタビューの「床屋のおじいちゃん」を「理容師のおじいちゃん」と代替えされたからだという。
「六十年も自分のことを『床屋』って名乗ってきた人間に俺はこの本を見せて何て説明するわけ?『床屋』は違反語だから別の言葉に置き換わってるけど気にしないとでも言うのかよ。『床屋のじいちゃん』であることに五十年間の職業意識やプライドや思い入れを持っていたうちのジジイにかよ!」
「床屋」という言葉は職業を卑小化した表現として実際に“放送自粛言い換え用”となっているらしい。「八百屋」「魚屋」「肉屋」なども同列にあり、何でも「~屋」という言葉には月の締め支払の売掛けではなく、日銭商売であることから真っ当な商いではないという意味があって、その商売を貶める表現なのだそうだ。まったくこういう発想にはただ驚き以外の何物でもない。
この章は前作で難聴者である鞠子に耳の不自由な本を紹介したとして小牧が連行された事件と同じ脈絡にある。「耳が不自由だけでヒロインになれない」という制度を作ったのが所謂「有識者」ということであれば、「床屋」を違反語と定めたのも「有識者」であって床屋さんたちではない。
有識者たちは「理容店」「理髪店」という言葉に置き換えることによって床屋さんたちを守っているつもりなのだろうが、「床屋」を卑賤な職業と決めつけていることに他ならないわけで、実はこれほど差別的なことはないというパラドックスだ。
日常、何気なく使っていた言葉がある日を境に差別語となって、そこで初めて一般社会に浸透していく。これは冗談ではなく日本語の危機であり、文化の損失に繋がっていく。
そうやって言葉を狩っていく団体があり、それに呼応する有識者なるものがいて、それらは何故か「正義」の虚飾をまとって君臨する。そしてそれらにいちいち反応するメディアの弱腰があるとすれば、何とも暗澹たる気分にさせられてしまう。
何度も書くが『図書館戦争』シリーズは図書特殊部隊に配属された乙女と教官のお馬鹿な恋愛物語には違いないのだが、そういった「表現の自由」を脅かす事例との真っ向勝負を描くものでもある。
何でもこのシリーズのアニメ化作品には中澤鞠子のエピソードは除外されたらしい。難聴者は本当にヒロインになることが出来なかった。その無念が有川浩を作家としてひとつ上のステージに押し上げたことは容易に想像がつくのではないか。
a:2513 t:1 y:0