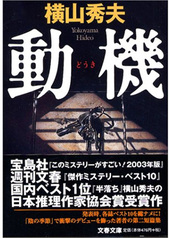◎動機
◎動 機
横山秀夫
文春文庫
いろいろと身につまされることの多い怖い連作短編集だった。
もちろん私は警察の管理部門に勤めたことはないし、刑期を終えて出所した前科者でもなく、まして女事件記者でもなければ裁判所の判事でもない。しかし、この「身につまされる」思いはなんだろう。一種の後ろめたさだといってもいい。
警察手帳が紛失する。前科が職場の人間の知るところとなる。自分が書いた記事が元で不買運動が起こる。あろうことか裁判の公判中に居眠りをしてしまった・・・。
横山秀夫『動機』に収録された四人の登場人物たちとはまったく別の畑で生きているにもかかわらず、どうしても彼らのミスを自分に置き換えてしまうのは、私が物忘れがひどく、よく物を失くす性質だからなのか。
まったくの他人事だが、その他人事であることに一抹の安堵さえ覚えてしまう。
【署内で一括保管される三十冊の警察手帳が紛失した。犯人は内部か、外部か。男たちの矜持がぶつかりあう表題作ほか、女子高生殺しの前科を持つ男が、匿名の殺人依頼電話に苦悩する「逆転の夏」。地方新聞の“男尊女卑”社会の中で女性記者が葛藤する「ネタ元」。公判中の居眠りで失脚する裁判官を描いた「密室の人」など四編を収録。】
『逆転の夏』は刑期を終えて出所した男に匿名の男から嘱託殺人が依頼されるという、本編中で最もフィクションの味の強い作品ながら、横山秀夫が優秀なストーリーテラーでもあることを見せつけた一編。
スリリングだしサスペンスも効いていて、何よりも最後の最後まで解明されない謎は驚きに満ちている。
ただ個人が組織の論理の中でもがき苦しむストレスを描く他編と比べるとややテーマが違うような気がした。この連作集に入れるべきではなかったか。
『ネタ元』では新聞社という男社会に生きる女性記者・永島真知子の葛藤が描かれる。
『陰の季節』での女性警察官の描き方とは同じ脈絡で、横山秀夫が女性心理の機微をリアルに描こうとするときは、対比する男をとことん俗物に設えてくるのが可笑しい。
そして横山秀夫が地方紙の新聞記者だったという経歴が見事に生かされている。とくに全国紙の攻勢や地方紙同士の足の引っ張り合いは凄まじいばかりで、矢継ぎ早に繰り出される取材合戦を短いセンテンスで区切ることによってスピード感を獲得している。
「弱者のために記事が書きたい」と入社時に挨拶した記憶が真知子の脳裏を空々しく蘇ってくる。
理想と現実とのギャップもまたこの連作短編集の大きなテーマだ。
『密室の人』は公判中に居眠りをしてしまった裁判官の話だ。
しかも裁判中に寝言で妻の名前を叫んでしまう。弁護人でも検事でもなく、裁判官が主人公という小説を初めて読んだが、そういう裁判官の失態を横山秀夫は記者時代に見聞きしたのかもしれない。
しかしその失態をネタに横山秀夫が次々と広げていく風呂敷がすごい。まず所長に呼ばれて今の妻との再婚時期が問責される。次にマスコミが記事に書くといい、弁護人が噛みついてくるという。まったく我々が仕事中に舟を漕いでしまうのとはレベルが違うなと思っていると、その後から話がさらに複雑さを帯びてくる。
短編集として、前作の『陰の季節』と双璧の出来栄えだったと思うと同時に短いページでここまでキャラクターを立たせる力量には感心する。私が短編に持っていた偏見がことごとく打ち破られていくのも、読書の快感ではあるのか。
以上、表題作以外の収録作品について短評を残しておく。
さて表題作の『動機』は前作の『陰の季節』に引き続き、署内抗争劇だ。
ところで、私の職場の同僚には警視庁OBが七人いる。管理官だった事務局長以外は全員、現場の捜査員だったのだが、彼らが日頃よく使う会話に「所詮は現場を知らない事務屋だから」というのがある。犯罪の現場を常に目の当たりにしている捜査員たちに、署内の椅子に座って仕事をしている人間を快く思わない精神風土が根づいているのがよくわかる。
いや警察ならずとも一般会社の外回りの営業と社内業務の間でさえ心情的な確執はつきもので、社屋の内と外で同じ価値観を共有することがいかに難しいことなのかは私も経験上身に染みていることだ。
「警察手帳は警官の魂」だと主張する刑事部の激しい抵抗を押し切り、手帳の一括保管を提案した警務部企画調査官の貝瀬。その一括管理の裏をかかれて手帳が大量紛失する。誰もがスケープゴートを探すような深刻な事態の中で、警務部の上司からは「君の案は裏目に出たな」「責任は貴様がとれ」とそっぽを向かれ、反目していた刑事部からは「それ見たことか!」となる。
孤立した貝瀬に身内からの援護はなく、残された時間はマスコミ発表までのわずか数日。犯行は外部なのか内部なのか。周囲の状況が間違いなく内部犯行を示す。この凄まじいフラストレーションの中でエリート警察官の内部捜査が始まる。
上にも書いたように現場で体を張る叩き上げの捜査官は概して中のエリートを小馬鹿にする傾向がある。曰く「現場を知らないくせに偉そうな口を叩くな」となるのだが、それ故に現場同士の身内意識は強く、警官の不正や規律違反を調査する管理部門に対しては、はっきり「敵」だと認識しているのかもしれない。
この『動機』が浮き彫りにさせている世界はそこにある。
フラストレーションの中でいくつものストレス要因が貝瀬を待ち受ける。実直な警察官だったという評判の父親は家庭を顧みることなく職務に明け暮れていたことも、その父親が今や精神病院の世話になっていることも貝瀬にとってはストレス要因だ。
そしてクロではないかと目星をつけた益川という盗犯係長。猛者として慣らす柔道の有段者。以前は荒っぽい取調べが訴訟寸前まで行ったことがある。すでに署長のポストが目にちらつき始めているエリートの貝瀬は、この一期上の厄介者と対決を余儀なくされる。
こういうストーリーなので大団円になっても爽快感はない。しかしズシッとした手応えにはカタルシスを感じる。
「俺はこんなことがやりたくて警官になったはずじゃなかった」というエリート警官の内なる叫びが60ページの短編の中に息づいていた。
さすがに表題作だけあってこの一編の素晴らしさはこの本の中でもひとつ頭が飛び抜けていたのではないだろうか。
a:2246 t:2 y:0