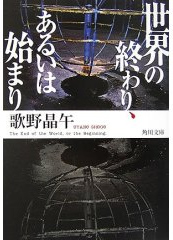◎世界の終わり、あるいは始まり
◎世界の終わり、あるいは始まり
歌野晶午
角川文庫
ほぼ夜を徹して一気に読んでしまった。 正確にいえばこの小説の持つ異様なテンションに読まされてしまったというべきか。
【東京近郊で連続する誘拐殺人事件。事件が起きた町内に住む富樫修は、ある疑惑に取り憑かれる。小学校六年生の息子・雄介が事件に関わりを持っているのではないかと。そのとき、父のとった行動は…。】
さて、何を書いたらいいものやら。ただでさえミステリーの書評は難しい。とくに歌野晶午『世界の終わり、あるいは始まり』のように展開にある種の仕掛けが施されているような小説に対し、書評などと大それたことを試るとなると内容に踏み込むことになり、さすがに辺境のページの書き手であっても禁忌を冒すのは憚れるというもの。
そういえば歌野晶午の名を一躍世に知らしめた、かの『葉桜の季節に君を想うということ』にまともな書評がついたのを目にしたことがない。このたび文藝春秋から文庫が出たので解説を期待して巻末をめくってみたが、案の定、解説はついていなかった。帯にある「やられた!の一言につきます。とにかく読んで騙されてください。」というコピーで購買客への煽りは完了だろう。
それほど私は『葉桜〜』を面白く読み終えた。「意外な犯人」「意外なトリック」とは別にミステリーの仕掛けどころはあるものだと驚かされた。
真っ白な気持ちで読むというのは理想的な読書のようであるが、作品と対峙するとき、実際に頭を空っぽすることなどまったく不可能な話で、必ず読者は先の展開を予想してページをめくる。それは芥川賞の候補にあがるような純文学ですらそうなのだから、ミステリーともなると絶対に無理。そもそも「やられたい」という欲求がある以上は自分勝手な先入観を膨らませるだけ膨らませた方が絶対に楽しみも倍増する。
むしろ、その先入観を植えつけていく作業も作家の見せどころで、読者の頭の中で膨張した先入観にどう落し前をつけるのかというのが、いわゆる作家と読者の勝負ということになる。予想した展開通りだと優越感は味わえるが充実した読書だとはいい難く、予想外の結末だったとしてもそれが腑に落ちなければ高揚感は得られない。それほどミステリーの読者は贅沢で尊大な存在といえるのかもしれない。
さて歌野晶午『世界の終わり、あるいは始まり』に話を戻す。
読後の昂揚感はあるのだが、それがカタルシスだと呼べるものなのかどうかは判らない。最後に作者が引用する「パンドラの壺」を救済として捉えるかどうかでも印象がまるで違ってくるだろう。
しかし描写力が凄い。正直、この作家がここまで「書ける」人だとは思わなかった。
改めて『葉桜〜』が大仕掛けのために文体を軽くしていたのだということがよくわかるほど、この小説は描写力で読ませてしまう。それが胸を突く。
“知り合いのあの子が誘拐されたと知った時、驚いたり悲しんだり哀れんだりする一方で、わが子が狙われなくてよかったと胸をなでおろしたのは私だけではあるまい”というナビゲートの短文にあるように、ここまで「当事者」であることのどうしようもない重みで圧倒させる小説も珍しい。
乱暴な言い方をすれば惨禍が起こったとき、当事者とその近しい周辺を除けば、すべては傍観者と偽善者しか存在しかいないのではないかとも思っている。
もちろん小説は小説であって、現実世界とは切り離していたい読者ではあるのだが、昨今の少年犯罪や刹那的な通り魔犯罪で語られる「別に誰でもよかった」という殺人者たちの口述を聞くにつれ、被害者はもとより、加害者の肉親が直面する地獄にまで想像が及んでしまう。想像するということは私が常に傍観者であり続けているということであり、「当事者にならないために人生をつつましく生きている」証しだともいえる。
この小説の主人公はその当事者になってしまうことで様々な地獄を周航する。一個人であろうが、それは間違いなく“世界の終わり”であり、その描写があまりにもリアルであるため、“あるいは始まり”と蛇足のような文言を付け加えられても、そこに救済の余地はないようにも思えてしまう。
読書中、私はこの小説の結末に至るまでいくつかのオプションを思い描いていた。それも傍観者である証しみたいなものだが、そのオプションをことごとく潰しにかかる歌野晶午によってバーチャルに当事者を意識させられてしまう。それが主人公と共鳴して異様なテンションになる。
この小説についてはここまでが書ける限界なのではないだろうか。
a:2912 t:2 y:0