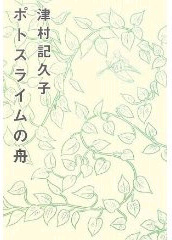◎ポトスライムの舟
◎ポトスライムの舟
津村記久子
「文藝春秋」三月特別号
そもそも純文学とは何であるのか?大衆文学とは小説の質が違うのかも知れないが、こんな個人のブログや読書感想文も含め、それこそ巷には玉石混淆、あまたの活字が溢れかえっているのに、このジャンルだけが純文学と大衆文学という明確な住み分けがされていることは、時代のナンセンスなのではないかという気がしている。
だから芥川賞受賞作が純文学の最高峰というイメージで津村記久子を読み終えたからといって、純文学の世界に浸ったという感慨はない。強いていえば芥川賞は文壇ビジネスに現れた有望新人の作品を、我が読書にチョイス出来る有り難い指標になっているということだろうか。
そうはいっても単行本ではなく作品全文が掲載された文藝春秋誌による読書なので、文壇ビジネスに寄与しているとはいえないのかも知れない。
【お金がなくても、思いっきり無理をしなくても、夢は毎日育ててゆける。契約社員ナガセ29歳、彼女の目標は、自分の年収と同じ世界一周旅行の費用を貯めること、総額163万円。そんなとき大学時代のシングルマザーが実家に転がり込んでくる。】
自分のような未熟な読者が小説を読むとき、その読書時間の短さが読後のカタルシスとほぼイコールとなるのだが、『ポトスライムの舟』は大きな物語のうねりがあるわけでもないわりには、テンポのよさで一気に読み終えることが出来た。
この物語の主人公は29歳の独身女性である長瀬由紀子。作品中に由紀子ではなく、ナガセと人称されていることが、作者が主人公と一定の距離を保っているようで心地よよい。変にポジティムでもネガティブでもなく、とびきりの明るさも希望もない代わりに陰鬱でも絶望もない。
なんとなく目指そうと試みる工場に貼ってあったポスターの「世界一周の旅」も別に自分探しの旅をはじめようという意志があるわけでもなく、強いていえば旅行費用が自分の年収と符合するのと、大学時代の講義で噛んだカヌーへの消極的な興味があるに過ぎない。とにかく三十手前にして日常にメリハリをつけようと足掻きたいのだろう。
しかしナガセをとりまく環境はワーキングプアの世相にあって、なかなか一筋縄にシングルライフを謳歌するというにはほど遠いようだ。
「“時間を金で売っているような気がする”と思いついたが最後、体が動かなくなった。働く自分自身ではなく、自分を契約社員として雇っている会社にでもなく、生きていくこと自体に吐き気がしてくる。時間を売って得た金で、食べ物や電気やガスなどのエネルギーを細々と買い、なんとか生き長らえているという自分の生の頼りなさに。」
そこそこ深刻に思い詰めながら「今がいちばんの働き盛り」という拠り所だけで毎日を浪費しているような感覚なのだろう。自分もこの感覚には共感する。だからナガセがメモに走り書きをする電車賃の無機質な数字の羅列や、花が咲くわけでもなく、後々、毒性があることが判明するポトスライムの増殖に彼女の心象を読み取ることも容易ではあった。しかし共感はすれど、決して身につまされるような共鳴までには至らない。男とか女とかではなく、皆がそんなものだろうという思いがあるからだ。そこが神経に触ることなく描かれているので読んでいて苦痛がない。
そういえばこの小説には男がほとんど出てこない。物語で進行する時間帯に出てくる男といえば工場の老いた守衛くらいなものだ。ナガセと大学時代の友人であるヨシカ、そよ乃、りつ子。幼稚園年長組のりつ子の娘・恵奈。ナガセの母親と勤務先の先輩・岡田さん。それぞれの女たちが、それぞれの生活感の中で暮らす中で、作者がナガセとほどほどの距離を置いているように、ナガセも彼女たちとの距離を微妙に測っているように思える。
だから「自分が何をしたらいいかわからないにもかかわらず、しじゅう子供に指示をだしている親は務まらない」と思っているナガセが、幼稚園児の恵奈とふたりで留守番をするハメとなったときの困惑ぶりが面白い。爬虫類や植物の図鑑をめくりながら紅茶を飲んでいる恵奈を見ながら「おいしいともまずいとも言わないので、おいしくもまずくもないのだろう」という時間を持て余していく緩い緊張感は本書の読ませどころなのではないか。
一連の厄介ごとがとりあえず決着し、ナガセが徒労から解放されたのかといえば、つつましく記していた金銭出納メモを開くのは止めようという程度のことで、とくに重い呪縛に訣別したという感覚ではないのだろう。人間なんてものは一日の中でさえも気分が上がったり落ちたりするものであり、主人公の気分が上がった状態で物語が終わったのは「共感の小説」としてはとても良かったと思う。
結局、芥川賞だろうが、純文学だろうが、共感が生まれれば、それは広義に大衆小説なのだといえるのではなだろうか。
a:1883 t:2 y:0