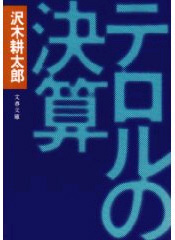◎テロルの決算
◎テロルの決算
沢木耕太郎
文春文庫
このノンフィクションは長い間、「読んでおきたい本」という位置付けにあった。
何度か賞賛する声を聞いていたこともあったが、本を読むという行為において沢木耕太郎『テロルの決算』は素通りすることは出来ないという不思議な決めつけが私の中にあったのだ。おそらく二十年越しの邂逅になるのではないだろうか。
何故、ここまでの時間の経過を擁したのかというと、小説家が創造するフィクションに読書の重きを置くという基本線があったことと、現実問題として書店で『一瞬の夏』や『深夜特急』『バーボン・ストリート』などは見かけても『テロルの決算』をなかなか探し出せなかったという事情もある。
今、読んだばかりの文春文庫の奥付を見ると、第一刷が1984年で1995年の時点で重版が十刷になっている。書店で探せなかったのはたまたま運がなかったということだろう。とにかく下手な小説化が描くどのフィクションよりも創造的であり、ドラマチックな渾身の一冊という読後感となった。
【山口二矢は日比谷公会堂の舞台を駆け上がり、社会党委員長・浅沼稲次郎の身体に向って一直線に突進した。自立した十七歳のテロリストと、ただ善良だったというだけでない人生の苦悩を背負った六十一歳の野党政治家が交錯した一瞬を描き切る】
この事件を初めて知ったのは高校時代に『仁義なき戦い』のオープニングの事件写真に被るナレーションで知ったくらいなので、思想的にはまったくノンポリだったのだが、あのオールナイトで何度も見た静止画は今に至っても強烈に脳裏に焼き付いており、それが私をこの本を読む機会を長年に温めてさせたひとつの起因とはなっている。
昭和三十年代は「政治の時代」だとよく聞く。『テロルの決算』はその最中の1960年10月12日。日比谷公会堂での三党首立会演説会で壇上に上がった社会党委員長、浅沼稲次郎が十七歳の元・愛国党党員の山口二矢の凶刃に倒れた事件を背景に、浅沼稲次郎と山口二矢のふたりの出自から、その瞬間までの人生を辿ると同時に民主主義と社会主義が激しく相克する激動の時代を活写していく。
しかしこのドキュメンタリーがある種の興奮と衝撃を伴ってくるのは、「浅沼委員長刺殺事件」という昭和の事件史を真ん中に置いて、そこから戦後史へと拡散させているのではなく、そういう背景を、ふたりの人生が交錯した一瞬の閃光に凝縮してみせたことに尽きるのではないだろうか。
「不意に歴史の表舞台に姿を現し、言葉少なく走り去った夭折者」である山口二矢について書いてみたかったという沢木耕太郎が、彼の生い立ちや近親者を取材する過程で、一方の浅沼稲次郎の「よろめき崩れ落ちそうになりながらも決して歩みを止めなかった愚直な一生」に人生の深い悲しみを見出し、そこで両者を同等の価値で相対させることで本書は名作になったのだ。
私がこの本で戦前から戦後、安保共闘からやがて経済高度成長に昇りつめていく日本の政治史を学ぶつもりはなく、ましてや浅沼稲次郎の物語から社会主義の系譜を、山口二矢から右翼思想の断末を知識として蓄えようとも思っていない。ましてや現代の社会情勢に照らし合わせてテロルという凶行に対して批判を展開することも、『テロルの決算』の読後感想文としてはひどく陳腐で無意味だと思っている。
息を呑むのは、戦前、戦後と時代の洗礼を浴び続けた社会主義の旗頭と、無垢で一途に生き急ぐ愛国少年という、立場も人生の経験もまるで違う両者が錆びついた短刀で一瞬の接点で交わるに至るまでの運命的な力学だった。そしてそこに見え隠れする通俗的に出来過ぎたエピソードがかえってドキリとさせて面白い。
悲劇であり、テロリズムという忌みすべき事件のノンフィクションに対して「面白い」という表現は不謹慎なのかも知れないが、浅沼稲次郎が凶行に倒れる前日に、浅沼は選挙応援にでかけており、かつてその候補を応援していた代議士もテロの凶行によって命を落としていたことや、その帰り浅沼を乗せた車が道に迷い、迷い込んだ場所が数日後に納骨されることになる多磨霊園だったこと。そして当日、浅沼がその日に限ってスーツを変え、いつも胸ポケットに入れていた分厚い手帳が入っていなかったこと、山口二矢が遅れて日比谷公会堂に到着したことで、入り口で面通ししていた公安警察が警戒を解いていたこと、愛国党の演説妨害で会場が騒然とした直後だったため警備の反応が一瞬遅れたこと。これらの偶然がことによると必然だったのではないかという「神の目線」で事件を眺めると、昭和史を震撼された事件という以上に私などはドラマチックな面白さで『テロルの決算』を読んでしまうのだ。
気鋭のノンフィクションライターは決して「政治の時代」の思想的解説やテロリズムへの警鐘という意図で本書を著したわけではないとしても、関係者への綿密な取材力と構成には十分に唸らせてくれるものがあり、とくに事件当日の山口二矢の日常と背中合わせの情景描写が次第に“その瞬間”までのカウントダウンを刻み始める刹那の緊張感の高まりは特筆すべきである。
a:3358 t:2 y:1