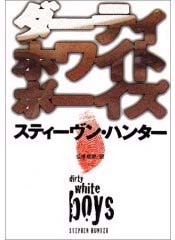◎ダーティホワイトボーイズ
◎ダーティホワイトボーイズ
スティーヴン・ハンター(Dirty White Boys)
公手成幸・訳
扶桑社ミステリー
スティーヴン・ハンターを続けて読むことにした。『極大射程』の主人公、狙撃手ボブ・リー・スワガーは四部作からなるシリーズだと知り、あの面白さが何度も味わえるのなら全作読まない手はない。ただ翻訳出版の事情なのか日本での刊行は前作『極大射程』よりも本書『ダーティホワイトボーイズ』が先になったと聞く。出版社も異なり、こういう混乱は翻訳ものにはよくあることなのだろうか。もっともリアルタイムで読んでいた読者が『ダーティホワイトボーイズ』から読んだとしてもまったく問題は感じないはず。本書ではかのボブ・リー・スワガーがたった一行の記述のみしか出てこないからである。
これは完全に独立完結したバイオレンスノベルの傑作だ。そうクライムのベルではなく、あくまでもバイオレンスノベルと称したほうが相応しい。
【重犯罪刑務所に収監されていた終身囚ラマー・パイは子分二人をつれて脱獄に成功する。生まれながらの悪の化身ともいうべきラマーとその一行は銃を手にいれ、車を奪い、店を襲い、警察を嘲笑するかのように、ひたすら爆走し、破壊しつづける】
ワルが主役の話。しかもラマー・パイは半端なワルではない。完全に倫理観のネジが外れ、情け容赦なく己の欲望に赴くままに死体の山を築き上げるタイプのどうしようもないワルだ。しかも最悪なことに無尽蔵の体力に甘いマスク、おまけにクレバーであるのだから凄ぶる魅力的なのだ。
私もスクリーンでは数限りなくワルが出てくる映画を観てきた。それに伴い相当のバイオレンスの表現をかなり受け入れてきたつもりでいる。しかし文章に於いてここまでの暴力性を味わったことはないのではないか。
冒頭の刑務所の殺人場面もさることながら、ラマーが怪力だが頭のイカれた従弟のオーデルと、軟弱だがインテリのリチャードを引き連れて刑務所を脱獄し、流血三昧の逃避行を開始する件では、ここまで血生臭くリアルにバイオレンスを活写しなくてもいいではないかと思えたほど、スティーヴン・ハンターの筆力が読むものを戦慄させてくれる。映像が視覚からではなく読み手の脳裏で創り出されてしまうので暴力が圧倒的なのだ。
そして困ったことにスティーヴン・ハンターの術中どおり、読み進めて行く間にこちらも次第にラマーに対する感情移入が芽生えてくる。暴力のエスカレートに対して感情が抑止ではなく欲求になってしまうとラマー・パイというアンチヒーローが読み手の中で誕生することになる。一種の酩酊に近い感覚だが、結果として限りなく愉悦に満ちた読書時間が出来上がってしまうのだから、かくも優れた作家の語り口というものは悪魔のごとく恐ろしいのだ。
さらにスティーヴン・ハンターはもうひとりの主人公を設定する。オクラホマ州のハイウェイパトロール巡査部長、バド・ピューティ。この人物はオールドアメリカンの父性を体現したような男。しかし優秀な警察官でありながらも部下の妻との不倫に悩む弱さを持つ。この弱さゆえにバドという人物にも読み手は共感しつつ、極悪人ラマーと相対しながら読み進めることになるのだが、共感しつつも否応なく悪の吸引力に揺さぶられていくことを体感していく。
もしバドが完全無欠のアメリカンヒーローであるならば、読者の嗜好によって二分されるだけの話なのだが、一方にも共感を覚えるとなると脳裏に葛藤が起こる。まったくこのあたりは良心をハンターに試されているような気さえしてくるのだ。
物語はラスとバドという対象的なふたりの対決を描きながら七百ページの長丁場を一気に駆け抜ける。作品中にバイオレンス映画の巨匠サム・ペキンパーに触れる件があるとおり、ニューシネマから七十年代のバイオレンスムービーの匂いがする作風が、映画批評家の顔を持つというハンターの一時期のグラインドシネマへのオマージュであるとも受け取れなくもないのだが、先程も述べたように『わらの犬』や『ダーティメリー、クレージーラリー』といった傑作映画よりバイオレンスノベル『ダーティホワイトボーイズ』はなによりもバイオレントだった。
a:2036 t:1 y:0