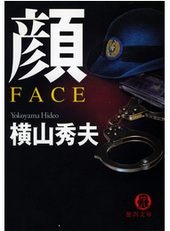◎顔 FACE
◎顔 FACE
横山秀夫
徳間文庫
『陰の季節』に所収の「黒い線」で、上司の理不尽な指示によって失踪騒ぎを起こした鑑識課の婦警・平野瑞穂をピックアップし、五編のエピソードでまとめた連作短編集。
例によって横山秀夫は23歳の女巡査を通して警察組織の濃厚な人間模様を描いていくのだが、男たちのギラついた野心と挫折を追及した諸作と比べるとさすがに女性が主人公なので幾分はソフィスケートされた書き味になっている。その点でやや読者を選ぶ作品なのかもしれない。
【 「だから女は使えねぇ!」鑑識課長の一言に傷つきながら、ひたむきに己の職務に忠実に立ち向かう似顔絵婦警・平野瑞穂。瑞穂が描くのは犯罪者の心の闇。追い詰めるのは「顔なき犯人」。】
多くの警察小説は事件に立ち向かう刑事を描いてきた。よって『陰の季節』や『動機』のように主人公が警務部の人事であったり、監察であったりすることは決定的に新しいことだった。さらに本作の平野瑞穂ように鑑識課で似顔絵を担当する警察官というのも、よくいわれる「横山秀夫は警察小説に新たな視点を持ち込んだ」という常套句のひとつに含まれるものかもしれない。
しかも女性警察官をヒロインとした数多の小説やドラマは、男の論理がまかり通る警察組織の中で「女だてら」に突っ張ったり、「男まさり」に突っ走ったりのスーパーヒロインとして描くことで、読者や視聴者には「組織の中で昇華する個」としてのカタルシスが喚起されるようなドラマツゥルギーになっている。
その点で本作のように「弱者であるゆえ健気」を重要なファクターに据えたことにも横山秀夫の革新性を見ることが出来る。
しかし『顔 FACE』が警察小説の中でも一線を画したものになっているとすれば、鑑識課の似顔絵警官にフォーカスを当てたからではなく、平野瑞穂のような女性警察官を主人公に置いて女捜査官ものを仕上げたことにあるのではないか。
現実に男社会の最たる警察組織にあって、女性警察官の存在は都合のいいように運用されてきた歴史がある。「採用当初は、警察をソフトに見せんがためのマスコットガール的役割を担わされてきた。世の中が交通戦争に突入した時代は交通部門に集められ、少年非行が増加したと世論が騒げば今度はひとまとめにして防犯部門に送り込まれた。いえばただもうその時代、時代の社会の風向きに翻弄され、個々の婦警の適性や力量などお構えなしに、単なる人数合わせの要因とみなされてきた」と横山秀夫が本文中で解説しているように、女性警官ものの多くはまずはこの「壁」を描くことになる。
収録されている『心の銃口』という作品では、拳銃のコンテストで優勝し、オリンピックの代表になることも夢ではない女性警察官が暴行されて拳銃を奪われるという事件が発生する。当然「だから女などに拳銃を持たせるからこういうことになるのだ」という空気が一斉に組織を駆け巡ることになる。
もともとちょっとした人間関係に傷つきやすく、運動神経にも自信がなく、拳銃を持たせるとぶるぶる震えるような平野瑞穂はこの「壁」の前に立ちすくむだけでしかない。「なぜ、ああまで軽視されながら我慢し続けるのか。震える小羊のように縮こまり、声もなく、存在すらなく・・・・」と常に自問自答する日々だ。
ところが傍から見れば一巡査である彼女が直面する「壁」など大した「壁」には映らない。市民生活の安全を守ることを使命とする警察であるならば、男たちが自分の中の男を競い合うような体質にもなるだろうし、世間に対して体面を繕っていくような組織にもなるだろう。そもそもお前はそれを承知で採用試験を受けたのではないかと。
本作がユニークなのは「壁」を主人公が鮮やかに突き破っていく姿に必ずしもカタルシスを求めていない点にある。むしろ「壁」は常に自分自身へと内向し、手を放してこぼれ落ちてしまえば楽になれるものを必死でしがみついていく彼女の健気さで読者の共感を得ようとする。
その点で横山秀夫の読者層に嵌る作品なのかどうかは疑問ではある。私は十分に「がんばり屋さん」として平野瑞穂巡査を応援したくなったが、もっともこういう共感は上司の七尾友子警部にいわせれば「婦警をマスコット的な扱う輩」から一歩も出るものではなのかもしれない。
ただ決して平野瑞穂は凡庸な女性警察官ではない。とくに事件に直面した際に発揮する観察眼などもっと評価されるべきだ。まして彼女の“本職”である似顔絵書きの描写にはプロフェッショナルのプライドを感じることが出来る。
「目撃者とのコミュニケーションであり、求められるのは聴取能力である。興奮している目撃者を落ち着かせ、同じ視点に立ち、決して誘導することなく確かな記憶のみを抽出して画用紙に具現化していく」。相当な才能が必要な仕事だ。
読者は共感だけで平野瑞穂巡査を応援しているわけではないのですよ、と、最後に七尾友子警部に書き残しておきたい。
a:1627 t:2 y:0