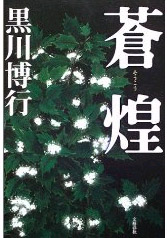◎蒼煌
◎蒼 煌
黒川博行
文春文庫
7月の頃、創元推理文庫『黒川博行警察小説コレクション』を読み終えるたび、これがシリーズ最高作ではないかという読書が続き、かなり幸せな気分を味わってきたものだが、この『蒼煌』を読み終えた今、本当の黒川の最高作はこれではないかと直感した。しかし警察小説の頃とは最高作という言葉の質感がまるで違う。
文庫版にして450頁以上。黒川作品として久々に読む大作だ。そしてどの黒川博行よりも重かった。最高作と書いておいて矛盾もいいところだが、この作家にここまでしんどい思いをさせられたのは初めてかもしれない。
【次期補充選挙で芸術院会員の座を狙う日本画家の室生は、現会員らへの接待攻勢に打って出る。名誉のためには手段を選ばない派閥抗争の巣と化した伏魔殿、日本画壇。師のために奔走する中堅画家や、振り回される家族たちは…。】
冒頭から360頁まで、物語の大半を芸術院会員への選挙運動で占められている。選挙運動といっても札束による票の買収工作だ。挨拶回りと称してカステラの届け物に百万円を仕込み、茶器の名品を届け、絵画を購入する。
七十過ぎの画家が八十過ぎの画商を参謀にして九十の老婆と連れ添いながらの東奔西走。実弾を受け取る側も皆、老人ばかり。その行脚が延々と繰り返されるのだから、しんどい読書になるのは仕方がないことで、正直にいえば黒川博行という才能豊かな書き手の筆致だから「読めた」部分も大きかった。
最高作だと直感はしたものの、素直に好きな作品かといわれると違う気もする。ミステリーでもハードボイルドでもない小説を、その両方に特化した才能を持ち、さらに主題に精通した作家の力業に圧倒されたとでもいっておこう。
例によって黒川は美術界の権威に対して猛烈なアンチテーゼを展開しつつ、億単位の札束を乱舞させることによって、それが権威としてではなく、巨大な権力として君臨している現実を活写させていく。権力が肥大すればするほど本来の権威は失墜していくという構図なのだろう。
しかし、骨董を「茶器の値段は由緒と箱書きで決まる」と言い切った黒川も日本画に対してはそこまで突き放してはいない。そこが短編集である『文福茶釜』とこの長編との違いなのかもしれない。
『文福茶釜』の読書評で書いたように、私は「この人は大学で美術を学び、高校で美術を教え、日本画家の妻をめとりながら一体、どんな気分で美術と関わってきたのか」と想像するのが楽しかったのだが、『蒼煌』には黒川の美術への愛憎があり、葛藤がある。決して楽しいという軽めの表現で片付けてしまえるものではない。
画家の売価が号当たりで決められていることは一連の黒川作品から知ってはいたが、絵画が土地と株と並ぶバブルの象徴だった時代では大家の評価額は号当たり千二百万まで膨らみ、それでも画商が持ち帰る途中で売れ先が決まっていたなどという話は想像を絶するものだし、画家が注文を維持して画料を上げていくには確固たるステータスを認められている公募団体に所属し、その中で地位を高めていく以外に道はなく、無所属の画家が大臣賞や芸術院賞といった大きな賞で顕彰される例はないという事実も驚きだった。
黒川作品の登場人物たちは、おしなべて欲望にとり憑かれている。もともと業腹な金銭欲に名誉欲が加味されることで、それは一層ギラギラと鮮烈なイメージとなる。しかし『蒼煌』にはそれを良しとしない清貧な理想が一方の核としてあり、その対比が「人間喜劇」としての面白さを際立たせているのではないか。
『蒼煌』というタイトルの意味が明かされる最後の一文に、美術界と関わってきた黒川博行の無垢な思いと抵抗を見る思いがした。
こういう読書評の真似事をする以上、文庫本巻末の解説には影響されない程度に読み流すとことを心掛けているのだが、「暴露小説、情報小説と捉えると、この物語の面白さを見失う」とする篠田節子の解説には全面的に同意したいと思う。それでも黒川が題材に選んだテーマから発せられる「情報」は相変わらず面白いのだが。
おかしな話をすれば、優れた脚本家に豪腕な演出家がいれば『仁義なき戦い・代理戦争』の域に達する映像作品に仕上げることが出来るのではないか。配役として加藤武、殿山泰司、小沢栄太郎、大滝秀治、梅津栄、内田朝雄、山谷初男、中村伸郎、金子信雄といった一癖ある顔が浮かぶ。今なら笹野高史は必須か。
a:3821 t:1 y:0