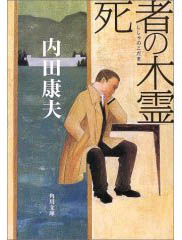◎死者の木霊
◎死者の木霊
内田康夫
講談社文庫
実をいうとこの『死者の木霊』を皮切りに、たかが2ヶ月余りのうちに既に20冊もの内田作品を読んでしまっている。きっかけは紹介だったが、1冊平均2日のペースで濫読しているのでないだろうか。
まず驚くほど「読みやすい」。初対面の人と会話をするときは第一印象が大いに影響するものだが、未知の作家の文章に触れる際も同じことを思う。表現のテクニックではなく、その作家自身のパーソナリティや人間性が私に合うか合わないかの問題は案外大きいのではないだろうか。
冒頭はいきなり濃厚な濡れ場から始まる。現時点で既読した内田作品でベッドテクニックの解説描写にお目にかかったのは後にも先にもこれだけ。有名な浅見光彦が33歳男性にしては不自然なほど禁欲であるだけに、この『死者の木霊』が自費出版されたデビュー作ということがこういうことからも伝わってくる。
【信州・飯田市郊外の松川ダムでバラバラ死体が発見された。捜査本部は「犯人」の自殺が確認された時点で解散となるが、この事件の背後に不自然なものを直感した飯田署の竹村巡査部長は執拗に事件に喰らいついていく。】
これが書かれたのは昭和五十五年。四十六歳では作家としてはかなり遅いデビューだ。
冒頭こそいきなりの濡れ場に驚かされたが、処女作にありがちな文章の硬質感や妙な気負いがないのも実年デビューであるためかもしれない。
物語そのものは、捜査本部が解散し、見做された事件に疑問を持った若い刑事の執念の単独捜査というありきたりなもので、とくに目新しいトリックで読ませるわけでもなく、『新宿鮫』並みに警察機構から独走する者への軋轢を組織論としてリアルに描出しているわけでもない。捜査描写にしても訪問先に予告せずに長野県警の一所轄刑事が青森まで出張に赴くなどの甘さも気になった。
しかし本書が飯田を皮切りに東京、青森、戸隠、鳥羽、軽井沢、松阪と転々と移動する舞台を主人公と伴走しているかのごとき臨場感を信条とする作品だとすれば、“旅情ミステリー”という内田康夫の代名詞に乗せられてしまったのも確かなようで、多少の急ぎ旅ではあったが、読後は帰路についた軽い安堵感のようなものを覚えた。
a:1909 t:1 y:0