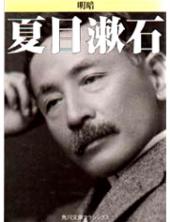◎明暗
◎明 暗
夏目漱石
角川文庫
いやはやしんどかった。宮部みゆきの大作を一週間で読み終えた直後だっただけに、何でも来いや!と勢いで手を出したものの、読了に一か月半もかかってしまった。[読書道]久々の更新となってしまったが、その間読書をさぼっていたのではなく、ずっと夏目漱石『明暗』と格闘していたのだ。
いや格闘していたといえばかっこいいが、寝しなや通勤電車で本をめくれば、ほんの数分で睡魔に襲われるという連続で、まったく遅々としてページが進んでくれずに悶々としていた。
流行作家のそれと違い夏目漱石の書評ともなると文学論というか学術的な研究書みたいな記事がネットに溢れているので、「いやはやしんどかった」みたいな書き出しのレヴューを検索してしまった人には申し訳ないが、私の読書なんてその程度のものだから真面目に資料を検索していた人は即刻退場なさった方が宜しいかと思われる。
【勤め先の社長夫人の仲立ちで現在の妻お延と結婚し、平凡な毎日を送る津田には、お延と知り合う前に将来を誓い合った清子という女性がいた。ある日突然津田を捨て、自分の友人に嫁いでいった清子が、一人温泉場に滞在していることを知った津田は、秘かに彼女の元へと向かった…。】
物語の表層を辿ればわざわざ小説にするほどの波乱万丈な展開はない。
痔漏で入院した津田という主人公は欠点こそいろいろと見て取れるものの、実に平凡な小市民ではあるし、妻のお延は個性的だが、その個性はこうして物語文学の中に生きているから個性的に見えるのであって、現実世界にはいくらでもいそうな、決してエキセントリックな女ではない。漱石はそんな夫婦の心理のひとつひとつを分析し、解説しながら進行させていく。
よく「行間を読む」などという。私が思う小説作法は登場人物たちの台詞のニュアンスや直接目にすることのできない表情を想像しながら読み進めていくものと確信していたので、登場人物の一言に心理解説が進行する構成はとてもではないが受け入れ難く、とくに人物同士の対決や確執を描く段になると実況中継の様相かと勘繰りたくなることしばしばだった。
このような構成の小説はあまり読んだ経験がなく、石原慎太郎『太陽の季節』や最近では西村賢太『苦役列車』がそんな感じの展開であったが、『明暗』ほど説明的ではなかった。強いていえば(いきなり通俗に落ちるものの)ヒロインの心情を逐一ナレーションで解説していた昔の昼メロのタッチなどを思い出してしまう。
しかし、いかんせん相手が夏目漱石ともなると、果たして「私が思う小説作法は」などと講釈を述るべき対象ではないだろうと大いに悩むところであり、ましてや昼メロなどを想起してしまうのはとんでもないとの誹りを受けるのだろうか。
そして中学か高校の授業で習った漱石晩年の境地である「則天去私」の思想。
天に則り自分を捨てるという考え方が『明暗』で著されているのかといえば、この小説はむしろ人間たちが随所で見せるエゴイズムが全編を覆っており、教えられた「則天去私」とはまるで真逆の世界が描かれていたので、これにも困っていた。
もっとも先述したように、身につまされるほど小市民的な俗物である津田と、エキセントリックとはいえないお延の夫婦は、エゴイズムといっても誰もが持つようなたかが知れたもので、それは「自分本位」と言い換えてもいい。
しかし「則天去私」は「自分本位」とは対極にある。もしかするとこの『明暗』はあくまでも「自分本位」だった津田に何かしらの転機が訪れ、やがて「則天去私」の心境に達するまでを描いた小説だったのだろうか。
そう、『明暗』は夏目漱石の遺作であり、未完の小説なのだ。
起伏のないストーリーに心理解説が終始する展開にもかかわらず未完という前提が、この小説を読むことのしんどさを増幅させていたのも間違いことないことだった。
そうはいっても「朝日新聞」連載中の『明暗』が突如絶筆となった大正5年の11月。
その時代の空気や考え方、現代人と何が違って何が違わないのかを読み取る作業は漱石を読む楽しみのひとつではある。『三四郎』を読んだとき、明治の若者の恋愛観が今と少しも変わっていないことを知って驚かされたのだが、86になる我が父親の生まれる十年も前の時代の息吹を『明暗』はよく描いているのではないか。
持つ者と持たざる者との差異は、例えば津田とお延が実家からの仕送りを止められ、金策に窮しながらも、一定の地位に安住して朝食にトーストとウーロン茶(!)を楽しみ、自宅に下女を住まわせている。それぐらい格差社会が問題とされる現代とも比較にならないほどの強固なヒエラルキーは存在していたと見るべきだろう。
そして小林という男の言動に『明暗』が描く時代の息吹を垣間見ることが出来る。小林はヒエラルキーの底辺にいながら朝鮮で活路を見出そうとして、上位にある津田に対して無心するどころか容赦なく罵倒してみせる。持たざる者に自我が萌芽し、その社会矛盾を告発するうえでの理論が体系化されたのがこの時期ではなかったかと思うのだ。これはなかなか興味深い。
さらに調べてみると、先述した「則天去私」の対極にある「自分本位」という概念で、その「自己本位」であるということも漱石の小説では重要なファクターになっているということだった。
そういえば『それから』の主人公も随分と自分本位な若者だったが、漱石にとっての「自己本位」とは、これも中学の国語の授業で習った漱石の論文『私の個人主義』に通じるところがあり、対極だと思われた「則天去私」も、「自己本位」から「則天去私」へと変化していったのではなく、「自己本位」は、人真似ではない生き方であり、後者は、自我に固執しない生き方であるという解釈で、この二つのロジックは両立しているらしい。
何だか解ったような解らないような話だが、それほど雲を掴むほどの難解さを感じるほどでもない気がするのは夏目漱石という文学者の資質なのではないだろうか。
さらに知識として知っている『草枕』における「非人情」という概念。夏目漱石に関しては苦しみながらも今後も読んでいくことになると思う。
a:2183 t:1 y:0