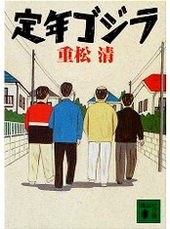◎定年ゴジラ
◎定年ゴジラ
重松 清
講談社文庫
カレンダーが新しくなると、ほんの少し前のことも途端に「過去」という言い方が相応しくなる。重松清を集中的に読んでいたのも二年前の夏に遡ってしまう。そして『ナイフ』に続いて読み始めたのが、図書館で借りた『定年ゴジラ』だった。
ところが帰宅の電車で読みながら睡魔に襲われ、最寄り駅で慌てて電車から飛び出した際にそのままブックカバーごと電車に置き忘れてしまい、図書館に返却期限の延長を申し入れ、しばらく遺失物で届けられるのを待ったのだが、とうとう紛失扱いとなってしまった。そこで新たにBOOK-OFFの100円コーナーで買い求め、弁償する前に一気に読んでしまおうと、130ページほどまで進んだあたりで完読するのは無理だとなり、途中で返却するという経緯があった。だから『定年ゴジラ』の最初の50ページくらいは今回の読書で3回目となる。
【開発から30年、年老いたニュータウンで迎えた定年。途方に暮れる山崎さんに散歩仲間ができた。先輩の町内会長、単身赴任で浦島太郎状態のノムさん、新天地に旅立つフーさん。自分の居場所を捜すリタイア四人組の日々の哀歓。】
『定年ゴジラ』はNHKでドラマ化され、私が重松清という作家を知るきっかけとなった。だから、重松清を続けて読みながら『定年ゴジラ』は大きなヤマ場になると思っていた。
それなのに何故、『定年ゴジラ』は一気に読むことができなかったのか。あるいは130ページまで読み進めていながら途中で諦めてしまったのか。あれだけ夢中になって読んでいた重松清の小説ならば、三日もあれば完読するくらい造作もなかったはずだった。
正直、あまり面白いとは思えなかったのだ。
『熱球』『ビタミンF』『流星ワゴン』は、リアルに同世代の主人公たちの焦燥や倦怠、あるいは情動で共感させてくれたし、『ナイフ』『エイジ』は、いじめや少年犯罪などの社会問題を背景に、少年や少女の感性が瑞々しく活写されていく様に率直にすごいと唸らせてくれた。
ところが『定年ゴジラ』で高齢者の哀感を綴られたときに、どうしてもそこに重松清のリアルさを見出すことができず、読みながらもブレーキがかかってしまったのだ。結局、紛失してしまったのも縁がなかったからだと完読は諦めてしまっていた。
調べてみると『定年ゴジラ』の単行本が出たのが1998年だということなので、小説誌に連載されていたとき、重松清は三十代の前半だったということになる。別にプロの作家に対して執筆年齢云々は問うべきではないのかもしれないが、私にとって「共有はできないが共感できる小説」という位置付けで、行間に執念のような熱気を感じて身につまされながらも読書の奥深さを実感していた重松清に対し、高齢者たちの姿を「さん付け」の三人称で想像と観察と取材で描くことに拭いきれない違和感があったのだ。
定年を終えた企業戦士の日常描写はいかにもありがちなことであったし、自己紹介のときに思わず名刺を出そうとしてしまう癖や、定年の先輩たちからの数々のアドバイス、通勤電車で読んでいたときは面白かったスポーツ新聞も自宅で読むと味気ないなどの「あるある」を並べているだけで、そこに重松清自身のリアルがないため、高齢者たちの心情に深く入り込めることができず、深刻な真実味よりユーモア小説の体裁をとろうと大阪弁から博多弁まで方言がごちゃごちゃになる野村さんを登場させたりしているのがどうも空回りを助長しているのではないかと思えて仕方がなかった。
ニュータウンくぬぎ台の模型を酔っ払ったゴジラたちが破壊する場面など、かなりの名シーンだとは思うが、同時に技巧を凝らしすぎているのではないかとも感じてしまうのだ。
そんな具合に既読の130ページまで到達するのに十日間ほど要してしまった。
そして故・鷺沢萌の解説を含む、残りの300ページは二日間で一気に読んでしまった。ここまでダラダラと批判めいたことばかり書いてしまったが、結果的にはその技巧にまんまとハメられてしまったのだ。
何よりも『第四章 夢はいまもめぐりて』で主人公の山崎さんに幼馴染の「チュウ」が訪ねてきて、故郷での子供時代や上京してきた母親との思い出を語るエピソードで果然、重松清の筆が冴えてきたと思った。
チュウが山崎さんに語る。「この街には勝った者と頑張った者しか残れない」という言葉。これでそれまでの『定年ゴジラ』の物語世界へのもやもや感が一気に消し飛んだ。
そう、いくら定年世代や老いることの哀感を切々と描いたのだとしても、彼らはバリバリの企業戦士として仕事を全うし、都心まで片道二時間かかろうがニュータウンに一戸建てを構え、孫に囲まれる人生を送り、定年後も年金と企業年金で再就職の必要なく、六十歳の若さで悠々自適の隠居生活を過ごしているのだ。やっかみ抜きにしても私があと十年後には逆立ちしても追いつかない境遇を勝ち得ている人たちばかりではないか。
嫁や孫に「おじいちゃんはぶらぶらしているの」といわれて酩酊するほど逆上する町会長など本人の勝手もいいところで、実際、それが許される立場にいるのだから結構なことではないか。
今の世の中には私を含め無数のチュウがいる。正確にいえば上記の台詞すら吐けずに沈黙しているチュウたちがいる。私はチュウの登場で、重松清がそのことを自覚していたことが嬉しかった。
そしてここに至って『定年ゴジラ』を善良なる小市民小説として読むことができた。少々、恵まれた小市民であっても、彼らなりに悩みはあるしドラマもある。当然、彼らも主人公の資格を有しているのだ。
山崎さんの娘の結婚話も、都会を捨て北海道に新居を求める藤田さんの生き方も、ニュータウンの現状調査のエピソードも、ひたすら技巧を楽しんでいればよい。もともと重松清は『ナイフ』のような隠々滅々な題材に対してもどこかに一縷の希望と爽やかな読後感を残すことができる技巧派ではないか。
終わりの方で山崎さんが奥さんと遊園地に行くエピソードなどは技巧の最たるものだ。
12枚撮りの使い捨てカメラに写されたスナップがカウントダウンのように消化されていく描写のあざといまでの上手さといったらないし、急死した野村さんの奥さんが生前に詠んだ短歌がパソコンのモニターに浮かび上がる場面の「泣かせ」など、喫茶店で読んでいて「周りの目があるから堪忍してくれ」と思わずにはいられない。
『定年ゴジラ』を途中で放り出してから二年間。憑き物が落ちたように重松作品を手に取ることはなかったのだが、こうして再び重松清の小説世界に戻ることになった機会と縁に感謝しなければならない。
a:2861 t:1 y:0