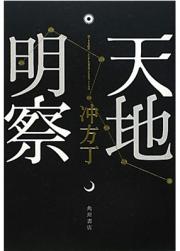◎天地明察
◎天地明察
冲方 丁
角川書店
算数、数学が大の苦手であり、方位や天体観測の類にも興味を持てず、囲碁など、定石はもちろんルールすら見当もつかない。よって、実在した渋川春海なる棋士であり天文暦学者の存在も知らず、彼が生涯を費やして成し遂げる大和暦の完成に至るまでの研鑽の数々もまるで理解が出来なかった。
そもそも「今有図如 大小方及日月円蝕交 大小方界相除シテ七分ノ三十寸 問日月蝕ノ分」などと算術の設問を出されたところで、私はただ空しくページを送るのみ。
しかし、それでも面白い。読書した直後に胸に残った思いは“すこぶる”つきの面白さだった。
【江戸、四代将軍家綱の御代に、ある「プロジェクト」が立ちあがった。即ち、日本独自の太陰暦を作り上げること。実行者として選ばれたのは渋川春海。碁打ちの名門に生まれながら安穏の日々に倦み、和算に生き甲斐を見いだすこの青年に時の老中・酒井雅楽頭が目をつけた。】
考えてみれば【読書道】始まって以来の時代小説。以前は司馬遼太郎、吉川英治から山田風太郎までよく読んだものだった。
時代小説といっても史実に基づかれたものから、まったくのフィクションまで様々だが、歴史という時代背景の中でいかに現代にも共感出来るような人間像を描けるかということが面白さの指標ではないかと思う。そこに歴史上に名を残す大物などが現れたりするとお楽しみは倍増する。冲方丁『天地明察』の面白さのすべてはそこに集約されているのではないか。
時代背景は動乱の戦国から徳川の世となり、やがて元禄の泰平を迎える直前。今でいうと戦後の混乱から脱して高度成長に駆け上がっていく昭和の一時期に似ていなくもない。
主人公の渋川春海は現代人の象徴として描かれているのだと思う。合戦も剣術も出てこない時代劇で、泰平に向っているとはいえ時代が動くことで、物語にある種のうねりが生じているようでもある。
冲方丁という作家は初めて知ったが、ライトノベルの書き手だという。その経歴が時代小説の型に嵌まることで硬軟自在の心地よい疾走感が生まれたのではないだろうか。
ライトノベルなるものの詳細を知っているわけではないが、心理描写よりも、ストーリーの面白さが第一義的に求められるジャンルだと思うので、渋川春海をはじめとする登場人物たちも単純でわかりやすく描かれ、前へ前へと物語を押し進めていく役割を果たしている。
だから算術や天文に関する専門的な描写が随所に盛り込まれても読書が立ち往生してしまう杞憂がない(もちろん、この方面に興味がある人が読めばもっと面白く読めるのだろうが)。
主人公は何度も打ちのめされて挫折する。その姿は慣れない二本差しに象徴されるように焦れったいほど、もどかしくもある。しかし失意の中で思わぬ人物から手が差し伸べ、様々な気付きを得て立ち上がるエピソードがカタルシスを生むことになるのだが、算術で求められる解答はただ一つであることが、物語の活き活きとした潔さを演出する効果があったのではないか。
算術道場の壁や神社の絵馬に書かれた「明察」「誤謬」「合間」「無題」「惜シクモ誤」等の採点文字に、それこそ“一瞥即解”の勢いを感じてしまう。
それにしても元禄以前の鎖国の時代にここまで高度な算学と天体観測の技術が日本に存在していたことが驚きだった。
“術を解することうかつなる者は、すなわち算学の異端なり”として、和算を考案し、主人公が生涯にわたって影響され続ける関孝和なる算術家は、微分・積分の一歩手前まで到達していたという。左様にこの本から教えてもらったことは少なくない。
一見すると「苔の一念岩をも通す」的な偉人伝ではある。諦めずに努力・精進すれば、いつしか夢は叶い、天を手中にすることも可能なのだという教訓の物語とも取れる。
しかし戦国の因習を打破し、文治国家を試みる権力があって、その背景に幕府と朝廷という敢然とした二重権力があり、江戸城内での権力闘争も絡めながら、会津肥後上・保科正之、副将軍・徳川光圀ら大物たちが物語を大きく旋回させることで偉人伝の色合いよりも大河ドラマ的な様相を呈していく。
また、関孝和に春海が出会いを果たす頃には、もう物語は七割近くを終えていたが、主人公の周辺には幕閣から公家、陰陽師、学者、そして市井の町民が集まる。それらの人物描写の掘り下げは浅いのだが、力感たっぷりの群像ドラマを構成しているともいえるのではないだろうか。
さて私が久々に新刊本を購入した動機は、本書が「本屋大賞」の受賞作であるからに他ならない。評論家や記者たちが選考する賞ではなく、書店員たちによる投票で選ばれるという趣旨が気に入っている。
「ぜひ読んで欲しい」「この本を売りたい」という熱意は信用出来るし、権威よりも意義に価値を見出したいと思うからだ。
もちろん、小川洋子『博士が愛した数学』、恩田陸『夜のピクニック』などの過去の受賞作が素晴らしかったことが大きいのだろうが。
北極出地の観測行脚で放たれた伏線を、次々と回収していく構成には、そのつど琴線を刺激され、クライマックスだと思われた改暦の詔の発布と、それ以降の大ドンデン返しに至るドラマトゥルギーは作家が読者を完全に掌に乗せて楽しんでいる風でもある。
そして、大団円では登場人物たちの「その後」が描かれるのだが、それが実に爽やかな読後感を残している。これは冲方丁が打った定石に我々が楽しく翻弄されたのかもしれない。
a:1969 t:1 y:1