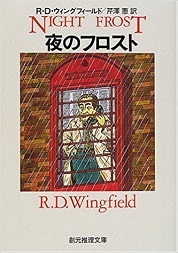◎夜のフロスト
◎夜のフロスト
R・D・ウィングフィールド(Night Frost)
芹澤 恵・訳
創元推理文庫
【肌寒い秋の季節。デントンの町では連続婦女暴行魔が跳梁し、公衆便所には浮浪者の死体が転がる。なに、これはまだ序の口で……。皆から無能とそしられながら、名物警部フロストの不眠不休の奮戦と、推理の乱れ撃ちはつづく。中間管理職に、春の日和は訪れるのだろうか?】
前作『フロスト日和』を優に超える784ページ。今までブックカバーが用をなさないほどの分厚い文庫本は何冊か読んできたが、それでも上下巻に分けられたものよりもずっといい。
まず一冊を完読した時の手応えが違う。それとミステリを読む場合、必ず謎の発端部を確認したい時にページを戻すことがままあっても上下巻に分けられるとそれが出来ない。さすがに普通の人は2冊持っては歩かないだろう。黒川博行の『国境』などあのボリュームだからこそ一貫した物語が堪能できるのであって、直木賞を取って売れる作家の仲間入りをしたからといって新刊がいきなり上下巻になるなど本当に勘弁してもらいたい。もともとが上下巻に及ぶボリュームの小説ならば仕方ないが、活字フォントを大きめにして行間に余裕を持たせ、300ページくらいの上下巻にして売り出す。出版不況の折、儲けたいのだろうが、読者はほぼ倍の金銭的負担を強いられてしまう。
世の中にいきなり値段が倍になる商品などありえないだろう、といいたい。
そのR・D・ウィングフィールド『フロスト』シリーズ全6作の半分は読んだ。残り半分から上下巻での読書となる。
もちろん水増し上下巻となっているわけではないのはすでに購入済みの残り3作6冊の文庫を見ればわかるのだが、本来なら一巻で読みたい典型的な内容ではある。
このシリーズの特色はモジュラー型警察小説ということで、事件が次々と速射砲のように勃発し、主人公のフロスト警部が右へ東へ奔走する姿を描くものなのだが、読書も上から下への奔走を強いられそうな予感がして、ややしんどくなりかけている。そりゃ短い間に続けて2000ページ超もガヤガヤした事件とフロストのドジぶりと下ネタ満載のセリフの連発を浴びて来たのだ。少々胃がもたれるのも仕方なかろう。
それでも『夜のフロスト』も面白かった。とにかく次から次へとページをめくらせる。読書中は帰宅にかかる時間もあっという間だ。なにせこれもまた年間ミステリベスト1に輝いた作品であり、そこに文句はない。まずそれをしっかり書き残す必要はある。そのうえで敢えて不満を呈する方向で以下の読後感想文を綴っていきたい。
まずジャック・フロストが所属するデントン警察署。この警察署の人事配置は一体どうなっているのだろう。ここがイングランドの所轄警察署であるのはわかるとしても、内容を読めばそこそこの人口と繁華街を抱え、近代的な都市型犯罪が頻発する治安状態にあることは間違いない。しかしこれまで3作を読む限り、デントン警察署がとても組織の体をなしているとは思えないのだ。
この『夜のフロスト』でいえば、“警視(スーパー)”と呼ばれる署長のマレットがデントン署の頂点にいるのはいいとして、その配下には警部のフロストと徹底効率主義のアレンがいて、その下に例によってフロストに散々引き摺り回される新米のギルモア部長刑事と、フロストから手柄を譲られるハンロンという部長刑事がいる。あとはインフルエンザの中で人手不足にストレスを沸騰させて笑わせる愛すべきウェルズ巡査部長と巡査が何人か出てくるのだが、今回の特徴であるインフルエンザが蔓延してデントン警察署の署員がバタバタ倒れる深刻な人員不足という事態を抜きにしても、あまりに組織が脆弱ではなかろうか。そもそもこの組織には一課も二課もなく、フロストは連続殺人事件から誘拐、強盗、窃盗、詐欺事件の類いまで捜査のすべてを抱えることになる。そんなことはまともな警察組織ではあり得ない。
そして作中、マレットが胸中を独白する。
「今、ここで自分が倒れでもしたら、デントン警察署の上級警察官はフロスト警部ただひとりになってしまう。いかなる理由があろうとも、本署の指揮をジャック・フロスト警部に委ねるわけにはいない」。
これには驚いて思わず付箋を貼ってしまった。薄々そうなのかなと思っていたが、フロストが組織のナンバー2だったことに改めて驚かされた次第だ。それではインフルエンザが流行ろうとも予め深刻な人材不足は変わらない。
本シリーズの最大の魅力であるジャック・フロストの不眠不休の行き当たりばったり捜査に、そんな過疎の田舎町の派出所並みの事情があるのだとしたら、結構、シリーズの根幹を問われかねないと思うのだが、どうなのだろう。
いくらモジュラー型警察小説であっても、警察小説を標榜する以上は背景はリアルでなければならず、そのリアルな組織からはみ出すことで物語は面白くなる筈なのだが、前提からモジュラー的な物語になるように設定されているのには疑問がある。
そしてもうひとつの不満はいつまでもマレットがステレオタイプの「自己中心で出世欲はひと一倍、保身に長け、場合によっては部下の功績も横どりする」的な嫌味な上司のまま描かれている点だ。いやそういうキャラクターが存在してもいいのだが、ただでさえ「少数精鋭」のデントン警察署にあって、いつまでもフロストにカリカリし、ギャフンといわせられるだけのコメディリリーフに終わってしまうつもりなのか、あまりに人物に幅がなさすぎる。たまにはフロストの獅子奮迅、八面六臂の奮闘を讃えるなり、世間やマスコミの批判から身を呈してフロストを擁護する男気があってもいいのではないか。そうすれば読者はフロストのみならずデントン警察署に訪れた災厄にもハラハラしながら見守ることになるだろう。
これはシリーズの蓄積から期待するところで、私は前作の『フロスト日和』で似たようなことをアレン警部に向けて書いている。
縦の人物配置は申し分ないのだが、もっと横にも広げられないものか。だからどうにも深味のないキャラクターの羅列に陥ってしまう。
そして何といっても最大の不満はこのシリーズ共通で引き継がれているアイテムの少なさだ。ジャック・フロストは『クリスマスのフロスト』の事件で瀕死の重傷を負い、『フロスト日和』ではあり得ないほどの膨大な案件をアレンを出し抜いてほぼ単独で解決して見せた。その功績がまったく『夜のフロスト』では顧みられてはいない。あれはあれ、これはこれということなのだろうか。これでは少々寂しすぎないか。いやフロストが気の毒すぎると感じてしまうのは私が『フロスト』シリーズにある種のヒロイックさを求め過ぎているからなのだろうか。
さらにそのフロストがシリーズを重ねる度にだらしない方向にエスカレートしているのも気になるところ。フロストのような古参刑事ともなれば、長年の経験で積み上げた捜査官としての矜持があってもいいし、組まされる若い刑事が最後はフロストに圧倒される展開が欲しい気もするのだ。前作はそれが最大の泣かせどころとして印象深かったのだが今回のギルモア刑事は最後までフロストを軽蔑して終わるし、実際、軽蔑されても仕方ない不始末をフロストは繰り返してしまった。
唯一、フロストが推理力を発揮する新聞配達のトリック。捜査官を集め録音機を執拗に検証する場面が好きなのだが、こういう場面がもっとあってもいい。
などと不満をぶちまけて来たが、ここで調べてみた。R・D・ウィングフィールドによる原書が出版されたのはシリーズごとにほぼ3年のスパンがある。要は読者は3年のスパンでフロストを楽しんできたわけで、私のように間隔もなく読み続けて来たわけではない。
創元推理文庫による翻訳ではさらに5年ほどのスパン。次回作の『フロスト気質』に至ると7年間も読者を待たせている。
そこで思ったのが、このシリーズを一気読みするのは止めてみようということ。少なくとも次のフロストに手を出すまで、間に3~5冊は挟もうかと決めた。それがベターだ。
『フロスト』シリーズがとびきりの面白さであり、全作が年間ミステリの1位に輝いた金字塔であることもまた事実なのだから。
a:660 t:1 y:0