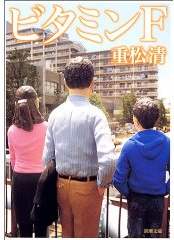◎ビタミンF
◎ビタミンF
重松 清
新潮文庫
一連の重松清への読書でひとつの不文律が出来た。
不文律とは大袈裟ならば、勝手に決めたルールといい直そうか。それは重松自身による「後記・あとがき」は目を通しても、このページをアップするまで巻末の解説だけは絶対に読まないということだ。
もともと完読の余韻を下手な解説がぶち壊してくれることは少なくないのだが、重松清を「共有と共感の作家」であると位置づけるならば、そこにはあくまでも物語を書いた重松清と、その物語を読んだ自分自身という関係性が純化されたものであるべきとの思いがあり、そこにアカの他人の「共感」を混入させたくないとの欲求がある。
とくに『ビタミンF』のような直木賞受賞作品ともなると、ちょいとネットを検索すれば選考委員の選評を含む数多のレヴューの類に遭遇することになる。それらは私と重松清の関係性に於いては不純物以外の何モノでもないのだ。
もちろん、こういう書評のようなものを自身のHPにアップする以上、不幸にもここに迷い込んでしまった方々にとって私自身がせっせと不純物をこしらえているという矛盾も自覚しているのだが。
【38歳、いつの間にか「昔」や「若い頃」といった言葉に抵抗感がなくなった。40歳、中学一年生の息子としっくりいかない。妻の入院中、どう過ごせばいいのやら。36歳、「離婚してもいいけど」、妻が最近そう呟いた…。一時の輝きを失い、人生の“中途半端”な時期に差し掛かった人たちを描く七編。】
重松清は昭和三十八年の早生まれなので、私よりも2つ学年が下ということになる。
早い話が社会に出た途端にバブル景気の一兵卒として、狂乱の中を奔走してきた世代だ。
『カカシの夏休み』にこんな科白がある。「バブルの頃は行け行けドンドンで働きつづけて、それが終わるとツケを払うので必死になって仕事をしてきましたからね。家のことなんかかまってなかったですよ」と。
ひと回り上の世代の作家が描く物語に団塊や学生運動への感慨が反映されるものが多いように、重松清が等身大の主人公を描こうとすれば20代から30代にかけてバブルの繁栄と崩壊を経験した登場人物が多くなるのは当然で、文庫本読書のタイムラグで、重松作品に多く出てくる38歳は殆ど私と同世代であるといってもいい。
私個人はそのツケを払う仕事が嫌で、未だバブルの残り香が漂う方へと吸い寄せられた挙句に転々とした結果が現在の体たらくとなってしまったのだが、多くの同輩たちは結婚して子供を作り、その子供たちがそこそこ手がかからなくなったと同時に気難しい存在になっていく過程に遭遇していることだと思う。なにせ家のことは奥さんに任せっきりの時間が長かっただろうから、それなりの齟齬をきたしている家庭も少なくないはずだ。バブルの盛衰は重松小説のドラマツゥルギーにとって欠かせないツールであるといえるだろう。
また一連の主人公たちの年齢を考えれば、まだまだ若さに対する強烈な名残を持ちつつも、壮年世代へのカウントダウンが聞こえてくることを自覚する年代となり、家族を描き続ける重松清にとって、そんな主人公たちのアイデンティティとは一体何かというのが重要なテーマになってくる。
いや、今の段階で既に『エイジ』を完読している感想でいえば、中学生には中学生のアイデンティティへの疑問があるのだから、総じて重松清の主人公たちは「自分の居場所とは?」そもそも「自分とは何か?」を常に問い続けている作家なのだろうと思う。
『ビタミンF』の“F”について重松は「Family」「Father」「Friend」「Fight」「Fragile」「Fortune」の頭文字をキーワードとした短編集を執筆したのだという。
もちろん、この『ビタミンF』という短編集ではなく、重松清の世界はそれらの“F”に彩られた物語ばかりだ。
正直にいうとフラジールな部分は読んでいて本当につらい。このつらさとは決定的な不幸に見舞われるとかではなく、たとえば『ゲンコツ』の主人公ように、実は「仮面ライダー」が大好きだが、それを臆面もなく披露する同僚を遠くで眺めていながら、そういうことを隠しつつ大人社会で生きている姿が読んでいてつらいのだ。
なまじ若さへの名残があるものだから、不良少年たちの「おやじ狩り」に腹を立てながら、自分世代がその対象にされていることが我慢できない。しかし、いざゲンコツを握りしめたときの弱々しさにも失望してしまう。高校に上がった頃に「喧嘩になったら親父に勝てる」と自覚した記憶が生々しいだけに困りものなのだ。
冒頭に「物語を書いた重松清と、その物語を読んだ自分自身という関係性が純化されたものであるべき」などと大層なことを書いた割に、個々の物語へのアプローチを放棄するようで情けないのだが、例によって言葉の名手は小難しい表現は一切使わずに、『ゲンコツ』『はずれくじ』『パンドラ』『セッちゃん』『なぎさホテルにて』『かさぶたまぶた』『母帰る』…。それぞれに十分に面白い七つの「Fiction」を一気に読ませてくれた。
a:1830 t:1 y:0