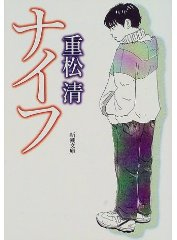◎ナイフ
◎ナイフ
重松 清
新潮文庫
薄々気がついていたことだが、こうして重松清を読み続けることは、根底に「怖いもの見たさ」を味わいたい気分があるのではないか。私には少なくとも「自分の境遇の方がマシなのではないか」と安心したいというセコい心理が確実に働いている。
『ナイフ』は今まで読んできた重松作品の中でも特段に“痛い”。
【ある日突然、クラスメイト全員が敵になる。僕たちの世界は、かくも脆いものなのか!ミキはワニがいるはずの池を、ぼんやりと眺めた。ダイスケは辛さのあまり、教室で吐いた。子供を守れない不甲斐なさに、父はナイフをぎゅっと握りしめた。失われた小さな幸福はきっと取り戻せる。その闘いは、決して甘くはないけれど。】
“痛い”どころか、ここまで怖い思いで読んだ小説は初めてだろう。
教科書やノートに落書きされる「死ね」「まだ生きてるの」「悪いんだけど、死んでくれない?」…クラスメイトたちから浴びせられる言葉の暴力に容赦はない。恐ろしいのは「あいつ、何か、むかつく」という、その“何か”には大した意味がないのだということか。
『ビタミンF』などの短編集では直截的にいじめをテーマに据えた話があったし、『熱球』や『エイジ』などの長編でもいじめは重要なエピソードとして挿入されていた。大人と子供の視線を駆使して家族のありようを描き続ける重松清にとって、子供の学校でのいじめの問題は避けられないテーマなのか。被害を受けている子供本人の、あるいは我が子の被害を知ってしまった父親の、それぞれの一人称で、重松は繰り返しいじめを描こうとしている。『ナイフ』はそれを特化させたということだろうか。
こういう作品の読書感想文を書くときの方向は悩む。単に『ナイフ』という著作物の良し悪しを重松清の作劇に沿いながら書いていく方向。あるいは『ナイフ』で示されたテーマをとっかかりに、例えばいじめ問題などについて私見を述べていく方向。そして、そもそもこういうテーマに挑んだ重松清の人となりを考えていくという作家論的な方向とが考えられると思う。
まあそれを全部中途半端に網羅しようとするのが私の悪い癖ではあるのだが、作家論的なことでいえば重松は幼少時に吃音で悩んでいたという経験が、『ナイフ』で描かれる少年・少女の物語とは無縁であるはずはないという気もするのだが、これは自伝的な作品といわれている『きよしこ』を読む機会があればアプローチしてみる必要があるのかもしれない。
作品で提示されたテーマや問題を、物語と切り離して書いていくことには多少後ろめたさは感じる。なによりもそれが私の大得意とするやり方だからでもある。重松清は『ビタミンF』のあとがきで「私はFictionの力を信じた」という意味のことを書いていたが、読書感想文である以上はどのようなテーマであっても書評は作品の範囲で完結するべきだというのは理想としてある。
しかし『ナイフ』の中で描写されるいじめのバリエーションは重松清の描写力もあるだろうが、物語を使っていじめの問題を広く考えてもらいたいという作家の意志も伝わってくるとなると、何となく書評の範囲で収めて問題提起から逃れることも不自然であるような気にもなってくるのだ。
そもそも、いじめなんてものは学級の中だけの流行り病ではなく、社会でも家庭でも間違いなく燻り続けているものだ。人間が自己防衛本能と集団心理と(多少の)弱肉強食の中で生きている以上は基本的には避蹴られないものだというのは確信に近い。ただ学級は実社会ほど純粋に富と利益のみに邁進する環境ではないというだけの話なのではないのか。
正直、中学、高校で私もいじめに加担したことはある。いじめを傍観してきたこともある。いじめという実感はないが、強者からいびられたことは何度かある。今でも自分と異質で思考が相容れない者は遠ざけたいという生理的な思いは否定しないし、同じ思いを共有する別の人間を見つけて安心したいという心理もある。しかしそれは自殺事件があったときに加害者側のひとりが「いじめられる側にも問題がある」とうそぶく内容と少しも変わらないのではないか。
上に重松清の「いじめのバリエーション」と書いたが、それはいじめのやり方という意味だけではなく、加害者と被害者の思い、そして家族のあり方までを問うという意味でのバリエーションだということ。
『ビタミンF』に収録されていた『セッちゃん』という短編は、主人公の女の子が転校してきたせっちゃんのどん臭さを面白おかしく両親に語って聞かせるのだが、彼女が一生懸命にセッちゃんを非難すればするほど、両親は次第に娘が自分自身のことを語っているのではないかと疑念を抱き、調べてみると案の定、セッちゃんなる転校生は実在していなかったというストーリーだった。本作での『ワニとハブとひょうたん池で』という作品でもそうだが、いじめられる側は両親や担任に自分の境遇を知られたくないというプライドが最後のギリギリの一線になっている。なるほど中学生の自殺事件が報道されるとき、両親が再三、学校に掛け合っていたという話が付加されることが多いが、実際はその手前でいじめられる側は悲壮な忍耐で踏みとどまっているのだろう。
重松清の凄いところはここまでいじめの傍証を言及していることだ。
息子がいじめられていることで、自らの少年時代を思い出して怖気づく父親。いじめに遭いながらも「逃げるな」という父親からのプレッシャーに追い込まれていく少年。いじめられながらもいじめっ子から離れられない少年の心理など、やはりそこには教育委員会が編纂する「白書」では読み取ることが出来ない、重松清のFictionの力がある。
a:4761 t:2 y:0