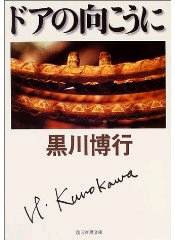◎ドアの向こうに
◎ドアの向こうに
黒川博行
創元推理文庫
「読書道」などとカッコつけてはいるものの、そもそもプロの読書家を目指しているわけではないし、完璧な書評を追求しているわけでもない。評価など二の次であくまでも「感想文」でいいのだと思っている。だから100点だの50点だの星3つだのという点数もつけていない。
今月に入って創元推理文庫による《黒川博行警察小説コレクション》を読んでいるわけだが、最後のページを閉じるたび「たった今、読み終わったコレが最高傑作なのではないか」と思わせてくれる。だから点数評価していなくて良かったとつくづく思う。
私自身が黒川のトーンにすっかり馴染んで、小説世界を楽しむ勘どころのようなものを掴んだともいえるだろうが、実際に黒川博行という男が作家としてのキャリアを積んでいくにつれて格段に語り口が巧くなったこと、作劇や台詞もこなれてきて場面の転換部分で意表をつくなど読者を手玉にとるようになったのは確かで、強引に野球に例えるならば速球一本槍で相手のバットをへし折ってやるという投球から、左右に揺さぶりながら、緩急の使い分けも覚えたという感じなのだ。
【頭部は腐乱、脚部はミイラ化、大阪東南部の橋梁工事現場で奇妙なバラバラ死体が発見された。後日、大阪北部で心中事件が発生。“ブンと総長”でおなじみ、大阪府警捜査一課の文田巡査部長、総田部長刑事に、京都人の五十嵐刑事も加わって事件を追う】
物語の半ばにして捜査本部はある登場人物を最重要人物として注目する。しかし刑事たちの心証はクロでも状況証拠ばかりで立件するには至らない。証拠の裏付けとトリックの解明に大阪府警捜査一課は奔走する。
黒澤明の映画に『天国と地獄』という名作がある。あれを高校時代に観たときには、身代金受け渡しの舞台となった「特急こだま」のサスペンスシーンに目を奪われたものだった。窓が開かないはずの特急でも洗面所のだけが数センチ開くことに気がつけば映画が作れるものだと意味不明に感心していたのだ。ところが、後年になって再見した時には身代金受け渡し場面よりも、警察署で延々と繰り広げられる捜査会議でのやり取りや、真夏の盛りに汗を拭いながらの地取り、聴き込みという地道な活動を丹念に重ねていくシークエンスに思わず唸っていた。あれは次第に追い詰めていくという“狩り”に似た快感が劇的な興奮を呼び起こすのかもしれない。
『ドアの向こうに』は、内容としては前作までにあったような銀行強盗、誘拐、現金強奪、車両爆破といった派手な仕掛はなく、容疑者と目された人物が死体であがるというドンデン返しを弄しているわけでもないのだが、「帳場」にて繰り返される会議、地道な捜査をじっくりと描写することによって“追い詰めていく快感”を喚起してくれる。
「それにしても十五年前の作品は懐かしい。ストーリーはきれいさっぱり忘れて、大阪文化と京都文化の軋轢を描いたものだとしか印象に残っていなかった。改めて読み返してみると、なんとガチガチのパズラーではおまへんか、(中略)この粗雑な頭でよくもまぁ、こんなややこしいトリックを考えたもんや、と感心してしまった。四十歳のわたしと五十五歳のわたしは、たぶんどこかに断層があって、人格が変っているのだろう」
と、あとがきに本人が記しているように、この作品は警察の捜査を通して描いた本格推理小説であり、雲を掴むようにぼやけていた事件の輪郭が次第に狭められて、やがて絞られた焦点のように真犯人が浮かび上がる構造が見事だった。やがて捜査本部の面々は舞台から消えて、クライマックスは総田、文田のコンビと犯人との一騎打ちの様相を呈してくる。その呼吸が心地よく、一気読みさせてしまうのだ。
あとがきの中でも触れているブンと五十嵐刑事の「大阪文化と京都文化の軋轢」も面白く読ませてもらった。ブンは前作『海の稜線』でもキャリア刑事相手に大阪と東京の文化対決を挑んでいるのだが、大阪と京都の方が隣人同士の濃さもあって対決としてはよりリアルだったように思う。
そのブンはこの物語の記述者であり主人公ということになるのだが、捜査の重要なヒントを母親と婚約者がもたらせてくるあたりに、黒川のブンへの愛着が一層感じられ、大団円の母子の会話などは清涼剤のような味わいでさえある。
とにかく処女長編『二度のお別れ』からそういう思いを重ねて5冊目となった『ドアの向こうに』を深夜のマクドナルドで100円コーヒーをお代わりしながら読み終わった瞬間のカタルシスはかなりのものだった。
a:1870 t:1 y:0