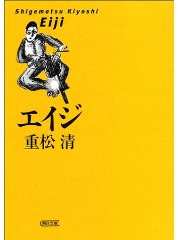◎エイジ
◎エイジ
重松 清
新潮文庫
中学生の話だ。重松清が『エイジ』を朝日新聞に連載を開始した前年に神戸の「酒鬼薔薇事件」が起こっている。明らかにあの事件にインスパイアされたのだろう。
実際、重松清は文庫本の巻末で「脳裏に顔にモザイクがかかり、声も性別がわからないほどひらべったく処理された少年が何人も映っていた」と語っており、テレビの少年たちが、犯人と同じ学校に通い、同じ街に住み、同じ年齢だということで取材カメラに収まっている図式に違和感を覚えたのだという。「容疑者とされた少年は、顔も声も名前も、建前としては一切報道されない。だからこそ、彼個人のプロフィールよりも、たとえば中学生だとか、十四歳だとかニュータウンに暮らしているとか、そういった属性をより強調されてしまうことになる」。そのモザイク少年たちを重松は、“少年問題”の壁紙やBGMのようなものだとして、それに反発するつもりで『エイジ』を執筆する。曰く、「モザイクの奥の顔が見たい、と思った」と。決して少年たちは一括りされるべき存在ではないのだという作家の強い気持ちが伝わってくる。
小説の感想文で物語に沿うより前に著者のあとがきを引用してしまったことに後ろめたさは覚えるものの、日本中を震撼された特異な事件をモチーフに、かくも普遍なる中学生の物語に仕上げた重松清に敬意を表したいと思っている。
【ぼくの名はエイジ。東京郊外・桜ヶ丘ニュータウンにある中学の二年生。その夏、町には連続通り魔事件が発生して、犯行は次第にエスカレートし、ついに捕まった犯人は、同級生だった―。その日から、何かがわからなくなった。ぼくもいつか「キレて」しまうんだろうか…?】
同世代の中年男たちの悲哀を真ん中に据えた家族の物語もいいが、ときたま短編などでお目にかかる少年(少女)一人称による重松小説は好きだ。重松が描く少年が実際に等身大にリアルな少年なのかどうなのかわからないが、重松の小説世界で呼吸する彼らは瑞々しいと感じる。プロの作家が追及するリアルであればいいと思う。
エイジは漢字で書くと栄司なのだが、父親はAgeの意味をこめて名づけたという。ときに大人から見る14歳中学生は得体の知れない生き物のように描かれることもあるが、中学生の立場からしてみれば、ある程度は大人の考えも本音も嘘も見抜けるようになってしまうことで失望する部分もあるのかと思う。それでいて一年半前は小学生。もしかしたら電車の切符を半年前は半額料金で買っていたのかもしれない。
『ビタミンF』などの一連の38歳が、まだまだ若さに対する強烈な名残を持ちつつも、壮年世代へのカウントダウンが聞こえてくることを自覚するという中途半端な世代であるならば、中学生自身だって自分が宙ぶらりんの中で生きていることを実感しているのかもしれない。
そんな思いの中学生たちが一堂に集う教室という空間に、ある種の力学というかバランスが生ずるのもわかるような気がする。「いじめ」「シカと」「キレる」「不登校」などはそのバランスゆえの現象なのではないだろうか。
などと他人事のように書いている私にももちろん中学生だった頃はある。というより私自身は14歳中学二年生のときが一番楽しかった。とくに何があったわけではないが、エイジと同じくバスケ部で汗を流し、ブルース・リーにとち狂い、女の子にちょっかい出しては廊下を逃げ回るのが好きな普通のスケベな中学生だった。
私のクラスにもエイジやツカちゃん、タモツくんはいたのだろうかと思えば、多少キャラは違えどもいたのだと思う。14歳の過ごし方など人によって違うのが当たり前で、「事件」が起これば一斉に一括りにしてしまう危うさは確かに社会の病理だといえなくもない。ただ当時の新聞の社会面で中学生の犯罪が特別に取り沙汰された記憶はないので、あの頃の中学生に対する世間的なイメージはずっと穏やかだった。なにせ「酒鬼薔薇事件」の時は14歳中学生が一種怪物扱いされていたのだから。
この小説はエイジの一人称で進んでいく。重松清の小説はどうやら主人公一人称形式が基本らしい。すべてはエイジの観察と心象の現在進行形だけでドラマは完結する。だから重松の筆が立ちすぎているため、エイジの感性が尖って読めてしまうのは仕方がないことだなのだろう。
例えば両親に姉ひとりのエイジの家族は、毎年子供の誕生日にはローソクを立てたケーキで祝う。そのやり取りが「ホームドラマみたいで嘘っぽい」とエイジは感じる。そして、そう感じる自分自身を「すねて黙りこくる息子もドラマでおなじみのような気がすると」とまで見えてしまうし、難産の末に帝王切開で出てきた自分を「人生のスタートの時点で、人間としてなにかとてもたいせつなものをはしょってしまった」などとも考えてしまう。
重松清が優れているのは、そこまで感性の鋭いエイジであっても、級友たちや片思いの女の子とのやり取りでは驚くほど子供ぽい言葉しか発しないこと。「かったりぃ」「うざい」「…べつに」「かっこわりい」。思考は尖っても、それを正確に言葉にすることが出来ないバランスのなさが14歳というものだろう。そんな不安定な時期に勃発した大事件。エイジは通り魔事件の犯人として捕まった同級生に自分を同化させてしまう。
人ごみを歩きながら、行き交う人々を脳内で次々となぎ倒していくという妄想は珍しいことではないはずだ。私自身もそれはやる。さらに罪を犯して帰ってきた級友が自分の席の前にいて、それがあまりにも普通の風景だったとすれば、「もしかしたら、自分もやってしまうのではないか」と思いつめてしまうのもわからなくもない。しかし他人に飛び掛っていく瞬間や、刃物が刺さっていく感覚までも想像してしまうと、相当にしんどいのではないか。エイジは通り魔に自分を重ねることで不安定なバランスの一方の負荷を極端にしたため比重が一気に傾いていく。このあたりの描写はエイジの一人称で物語自体が深化していくようでドキドキしてしまう。
『エイジ』は少年犯罪を描く小説ではない。前述した「すべてはエイジの観察と心象の現在進行形だけでドラマは完結する」は間違いではないとしても、きちんとモザイク少年たちの顔の奥を見つめた群像劇にもなっているし、結果的には成長物語としての味わいも残している。
では何故、『エイジ』が成長物語足りえたのかというと、穿った見方をすれば、この小説は重松清が「キレる」という心理の答えを求め続けた物語であるといえるからではないか。エイジは「キレた」経験がない。しかし部活仲間に囲まれ挑発されたとき、「キレろ、キレろ…」と自分に念じる場面があり、担任の先生にいわせると、もともと紐がゆるゆるに縛ってある奴は心配ないそうだし、姉にいわせると、あんたはキレてもすぐに結び直せるのだという。エイジは「キレる」という言葉は我慢や辛抱などの感情の抑制がプツンとキレるのではなく、自分と相手との繋がりが煩わしくなって断ち切ってしまうことが「キレる」ということではないかと考える。それが出来るかどうかでエイジは切実に壁を突き破ろうとする。
“キレたい。あとで結び直してもいいから、いまは、ぼくにつながれていたものをぜんぶ切ってしまいたい。ぼくは「中学生」で、父と母の「息子」で、姉の「弟」で、岡野やツカちゃんやタモツくんの「友だち」で、本条めぐみの「カレシ」で、相沢志穂に「ひきょう者」と言われ、タカやんの「同級生」で、バスケ部の三年生の「後輩」で、一年生の「先輩」で、「十四歳」で、オトコで、「ぼく」で……。どれから断ち切っていこう。どれを断ち切れるだろう。”
「あとで結び直してもいいから」というフレーズがとてもいい。もがきながら、とりあえず突破口を見つけようと必死なのがいい。
おそらく重松清も「キレた」ことなどないに違いない。
a:3761 t:1 y:0