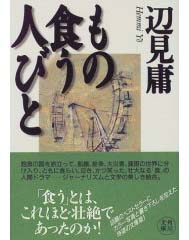◎もの食う人びと
◎もの食う人びと
辺見 庸
角川文庫
【飽食の日本に苛立ち、極貧と紛争と飢餓線上の風景に旅立つ。ダッカの残飯から戦乱のソマリアの粗食、チェルノブイリの放射能汚染スープまで、食う食う食う。人々の苛烈な「食」の交わりなしには果たせなかった渾身のルポルタージュ。】
読む者の誰もが自らの内にある偽善と葛藤するのではないか。しかし、我々は葛藤すればよいのだが、辺見庸は最初から偽善と格闘している。まさに自傷との神経戦、迫真のルポルタージュだ。
飢餓や紛争地区での命懸けの滞在レポ自体はとりたてて珍しいものではない。しかし貧困にしろ戦乱にしろ、それは表層にある情報の単なる一断面にしか過ぎず、事象の迫真性は伝わってくるものの、そこに身を置く人々の本質的な空気感全体をリアルに映し出すものであるのかは甚だ疑問に思う。
空気感という言い方がいかにも抽象的でありすぎるというのなら、生活感と置き換えてもいい。その生活を支えるうえで最たるものが生き物の根源的な営みであるところの「食」。富んでいようが貧していようが、とにかく生命を維持するために人は食わなければならない。その「食」を共有し、「味覚」が内包する人々の原始的な記憶を追体験することで辺見庸は世界を、そしてその対極としての“飽食ニッポン”を映し出していく。
『もの食う人々』は深作欣二が石橋蓮司をレポーターに起用して映像化した際に知った原作で、洒落でも何でもなくいつか食ってやろうと思っていた本だった。
辺見がこのルポで食するものは、バングラデッシュの捨てられた残飯、バンコクの安い労働力で生産される日本向けの猫用の缶詰、東ドイツの囚人食、ソマリアの難民向け援助食料と国連平和維持軍の各国携帯食、コソボの修道院の精進料理、ロシア海軍の給食、チェルノブイリの放射能に汚染された食品などだ。
そしてアジアからヨーロッパ、アフリカに至る人々たちの「食」を共有しながら、辺見は世界を描き、人間を描き、逆をいえば現実にある日本の飽食、宗教を軸とした民族間の紛争、国際救援活動という名のアメリカ主導による軍事行動など、一見すると国家社会の体制批判一点張りに走りがちな事象を突きつけられながらもあくまでも「食」の領域に踏みとどまろうとする。
それが辺見の力技とも潔さともいえるが、一言でいえば誠実なのだ。例えば「ソマリアの復興人道救助にかかる予算が1億6千6百万ドルに対し国連の軍事活動費が15億ドル以上」という矛盾は矛盾としても、そういった情報の裏付けを検証するのではなく、ものを食うという根源的な行為から様々な矛盾を炙り出していく。
「私はある予兆を感じるともなく感じている。未来永劫不変とも思われた日本の飽食状態に浮かんでは消える、まだ曖昧で灰色の小さな影。それが、いつか遠い先に、ひょっとしたら“飢渇”という、不吉な輪郭をとって黒ずみ広がっていくかも知れない予兆だ(中略)確かめようもなく、ただ曖昧な灰色の影を胸に帯びて、私はこの国をあとにする。」
という旅立ち前に記した冒頭文に、文明への警鐘という着地点を意識する辺見の姿勢が窺えなくもない。
しかし日本人の飽食をここで批判することに何の意味もないことを辺見はどこかの段階で悟ったのではないだろうか。それが残飯を食った最初のダッカかもしれないし、ホーチミンからハノイへと縦走するベトナム銀河鉄道の車内かもしれない。或いはセルビアの孤独な老女アナが涙混じりに小麦粉を練って作ってくれたレザンツェを食べた瞬間なのかもしれない。
飢えで明日には死を迎えるであろうソマリアの少女ファルヒアの最期を見届けることもなく、飽食の国の代表として「食」の取材に奔走していく自らの姿を読者に晒しながら、自身の存在矛盾と格闘している辺見の姿をどうやら我々も感じとっていく必要がありそうだ。
本書は、ものを「食う」という根源的な営みを様々な事例で突きつけられながらも、「食べものを無駄にせず、与えられることの感謝を忘れずに」というステレオタイプの偽善が、本当に偽善でしかなかったという、まさに格闘と葛藤のルポルタージュといえる。
一方、このルポルタージュが到達したひとつの境地として、菩提樹が並ぶ肥沃の土地で弾丸に怯える人々。チェルノブイリの荒涼とした風景に留まる人々も含め、ある種の「人間喜劇」に行き着いたのではないかとさえ感じてしまった。出会えたことの幸福を噛み締めておきたい一冊だ。
a:3220 t:1 y:1