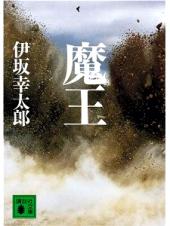◎魔王
◎魔 王
伊坂幸太郎
講談社文庫
「未来イコール老後でしかねぇよ」
「この世の中で一番贅沢な娯楽は、誰かを赦すことだ」
「おまえ達のやっていることは検索で、思索ではない」
佐々木譲の警察小説を六冊続けて読んで、佐々木譲からは絶対に出てこない台詞の数々にニヤリとさせられる。こういうギャップは面白い。そんなことで伊坂幸太郎の読書に戻ってみた。
【政治家の映るテレビ画面の前で目を充血させ、必死に念を送る兄。山の中で一日中、呼吸だけを感じながら鳥の出現を待つ弟。人々の心をわし摑みにする若き政治家が、日本に選択を迫る時、長い考察の果てに、兄は答えを導き出し、弟の直観と呼応する。】
兄は自分が思うことを他人の口からいわせてしまう「腹話術」の技を持ち、弟は勝負ごとには絶対に負けないという不思議な能力を携えている。そんな兄弟の姿を『魔王』と『呼吸』の二編で描く物語だ。
しかし独特の台詞回しや表情豊かな語彙は伊坂ワールド以外の何ものでもないが、この『魔王』は私がこれまで読んだ九編の伊坂幸太郎とやや趣を異にしていたように思う。
伊坂作品にはストーリーは一応終結しているのだが、その後の世界観をいつまでも読者に想像させるという後味に“イメージの余韻”があったはずなのだが、何故だか『魔王』ではストーリーそのものが終結していないのではないかという「投げ出され感」が強く、読後の“イメージの余韻”も随分と希薄なものになってしまった気がする。
文庫巻末の解説で知るのだが、この『魔王』の世界観は『モダンタイムス』という作品に引き継がれているのだということ。しかし余韻を味わいたかったら続編を読まれたしというのも乱暴な話で、伊坂自身、この作品にはエンターティメント作家として読者を楽しませたいという意識はそれほど強くなかったのではないか。そのことは「自分が読んだことのない小説が読みたい。そんな気持ちで書きました。」というあとがきの文面からも窺えるような気がする。
しかしそこで伊坂本人が「この物語の中には、ファシズムや憲法、国民投票などが出てきますが、それらはテーマではなく、そういったことに関する特定のメッセージも含まれていません。」と読者に説明しまうのはどういう料簡なのだろう。
この作家は直截に政治的なメッセージを発信することにある種の惧れを抱いているのではないか。または自らの著作が政治的な扱いを受けることを嫌悪するスタンスをとっているのではないか。何れにしても作家自身かわざわざ「あとがき」に書いて、読書の自由度を奪うべきではない。政治的なメッセージを含むつもりがないのなら、ストーリーとしてそれを反映させて読者を納得させることが物語作家の使命ではないだろうか。
確かに起承転結が曖昧となって、伊坂幸太郎にしては物語の着地点が見えない作品とはなった。しかしこれをメッセージ小説だからだと読者が受け取ったとして、それを阻害して否定する意味はなにひとつないはずだ。私は普通に政治色の強い作品を伊坂幸太郎が書いたものとして『魔王』を読んだ。
この作家のことなので直截的に政治批判を語ることはないが、発信すべきメッセージはしっかりと発信していると思うし、それを受け止めるべきことはしっかりと受け取ってもいいのではないかと思っている。
そこで話は変わるのだが、伊坂幸太郎は仙台の在住で、多くの作品は仙台を舞台としている。
そして、こうして駄文を綴る今も3月11日に三陸を襲った大震災の渦中にある。
震源の深さがマグニチュード9、大津波が岩手から千葉までの太平洋沿岸を襲い、死者行方不明者が2万人を超えるという大惨事で、伊坂自身は震災禍から逃れたというが、「国家存亡の危機」とまで謳われている災害は福島第一原発を破壊し、首都圏に計画停電が発令され、今なお放射能漏れの脅威に晒されているという現実にある。
実をいえば、こんな状況の中でのんびりと読書感想文など書いている場合かという思いもあるのだが、もし今『オーデュボンの祈り』や『終末のフール』を読んだとしたら、作品の印象は随分と違ったものになっていたに違いない。
今の日本に問われているのが政治のリーダーシップであり、たまたま仙台という符号が一致してしまったが、こうした終末を匂わす物語から政治色は決して逃れられるものではないのだ。
この『魔王』において、伊坂はファシズムの台頭を危惧している。憲法改正や国民投票のからくりをひとつの欺瞞として登場人物に語らせ、主人公には国中が諦観し、溜息が充満している中で、諦観と溜息の先にやって来るものに惧れを抱かせている。そういう目に見えない力が押し寄せてくる恐怖や、自分以外の世間がそのことに対して無自覚に日常を送っていながら、次第に取り込まれつつあるという不快感など、この小説はよく書かれていると思うのだ。
不幸の訪れを予感させる物語を不幸の真っ只中で読むというのも滅多にあることではないが、現実はこの小説の世界観のように、人々は溜息をついても、とても諦観したり無関心に日々を過ごせたりできる状況ではなくなっている。ある意味、多少のファシズムであっても強固なリーダーシップを望む声さえ出るのではないか。
作中に「深刻な夫婦喧嘩の最中には、憲法改正や自衛隊なんてどうでもよくなる」という意味の台詞がある。それは実にもっともなことなのだが、今は夫婦喧嘩そのものが幸せであることの証明となってしまったのではないか。
目に見えない力に不安を抱くより、目に見える恐怖に驚愕している現実のなんと不幸なことなのだろうか。
a:1945 t:1 y:0